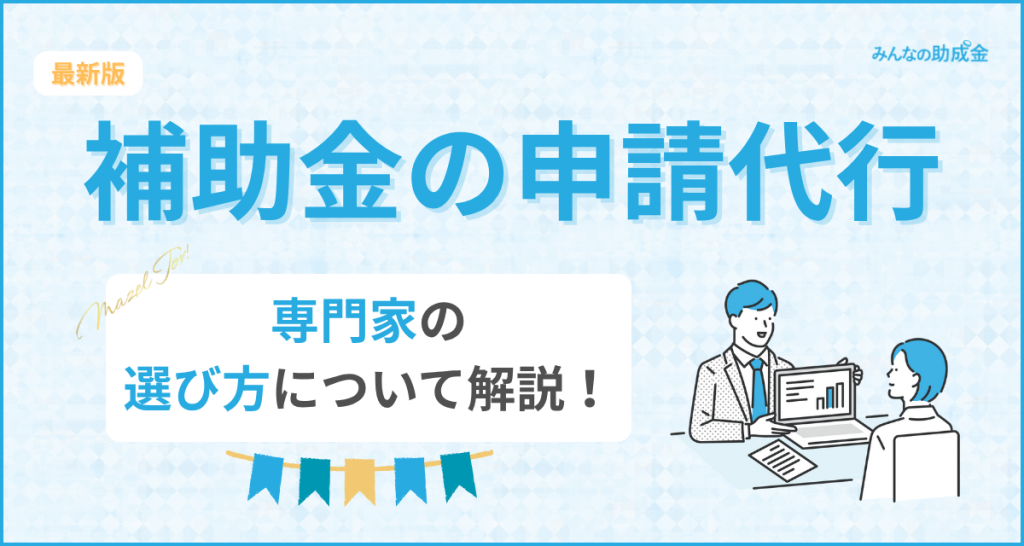
補助金・助成金を申請したいと考えたとき、課題となるのが「申請やその後の手続きをどうやって行うか」という点です。
中には、知り合いなどから「自分は専門家に頼まずに通した。誰でもできる」などと言われたことがある方もいるかもしれません。しかし、多くの申請者は、専門家の支援を受けて申請しています。
この記事では、専門家に頼む意義や、依頼する場合の選び方などを解説します。
補助金・助成金の申請代行
専門家に頼らず、自社申請をする事業者もいるのは事実です。しかし一般的には、専門家に依頼し、きちんと支援をしてもらったほうが、より採択されやすくなります。
まずは、自社での申請が難しいと言われ、専門家に依頼する人が多い理由を明らかにします。
自社で申請するのはなぜ難しいのか
自社で申請し、採択を受けて入金までの手続きを行うのは、非常に難しいと言えます。
また、仮に可能であったとしても、そのために人を雇ったり、事業主の貴重な時間を使ったりするよりも、専門家に頼む方が効率が良いと言えるでしょう。
そのように言える理由には、下記のようなものがあります。
補助金の申請要件が難しい
補助金・助成金の申請では、「要件を満たしていること」を示すのが最も重要かつ大前提のポイントになります。
また、他の事業者に比べて優れた計画であることを示さなければならない補助金では、特に審査のポイントになる部分で優れていることを示す必要があります。
ところが、多くの補助金・助成金ではこの「要件」や「審査ポイント」の数が非常に多い上、「どのように満たしているのか」まで書かなければならない項目も多いのです。
公募要領のあちこちに書かれている要件や審査ポイントをすべてピックアップし、満たしていること、優れていることを記述するのは、簡単なことではありません。
補助金・助成金で使われる用語が分かりにくい
補助金・助成金の審査は、行政側の論理で行われます。
「お役所の使う言葉や論理は、経営者とは違う」「お役所の文化は自分たちとは違う」。そう感じたことがある方は少なくないでしょう。
しかし申請では自社の取り組みを、そういう人たちにも分かるように書かなければならないのです。
経営者同士なら伝わるものでも、そのまま審査に使えるかどうかはまた別のお話になります。両方の言葉を理解できる人でなければ、うまく伝えるのは難しいのです。
必要書類が多く複雑な手続き
「びっしり詰まった文字を読んだり、難しい書類を扱ったりするのは苦手」という経営者は珍しくありません。
業種によっては普段の業務でそれほど書類を扱う機会がなく、社員も含めて得意な人がいない場合もあります。
補助金・助成金の申請では、形式も内容も整った正しい書類を揃えなければなりません。
中には決算関係や経営そのものにかかわる書類など、一介の事務員に扱わせることをためらうようなものも含まれます。
いざ申請というときに「アレがない、コレがない」では、締切に間に合わないことも。さらに、せっかく提出しても、証明書の種類が間違っていたり、法定の書類に重大な不備があったりしたら、審査で落とされてしまいます。
専門家に依頼するケースが多い理由
では、書類を扱うのが苦ではなく、難しい内容もじっくり向き合って解決できるような経営者であれば、自社申請で十分と言えるでしょうか?
そうとも言えません。専門家に依頼するのは「自社では難しいから」という消極的な理由だけではなく、「専門家に依頼したほうが得になる」という積極的な理由もあるのです。
申請書の書き方次第で採択率が大きく変わる
申請書にどんな項目が必要であるかは、もちろん公募要領や様式に記載されています。
しかし、その必要な項目をどのような形式で、どのような順で、どのような論理構造で、どのような図表をつけて書くか、どんな別添書類を作るかは、自由演技になります。
専門家の腕の見せ所はその部分です。より効果的な申請書類は、他社との競争があるような補助金の採択率を大きく上げます。同じ内容であっても、見せ方によって説得力が変わるのです。
制度や審査基準の理解が必要
ときには記載事項の中に、基本的な法律や制度の理解を必要とするものもあります。
たとえば一部の申請では、労働者名簿や賃金台帳を求められます。単に名前を並べた名簿や支払いの記録を出せばよいと考える方も多いのですが、実はこれらの書類の形式や内容は法律で定められているのです。提出した書類がその形式を守っていないものであれば、不備扱いになります。
また、審査がどのような基準で行われるかを理解するのにも、特殊な知識が必要です。
その補助金・助成金がどのような位置づけやねらいで行われているのか、個別の補助金・助成金が重視しているポイントは何か、そんな部分の理解も、書類の精度に影響してきます。
これを個人が手に入れるには時間もかかり、経験してみなければ分からないこともあります。せっかく頑張って手に入れても、その知識は自社の1回しか使えません。
一方専門家は複数の事業者を支援しているので、学ぶ機会も多い上、その知識を何度も使って、1回あたりのコストを下げられるのです。
金額が大きい(数百万円〜数千万円)案件ほど専門性が重要
1万円の買い物と、100万円の買い物とでは、買う前にどのくらい調べるか、買うときにどのような期待をするか、まったく違うでしょう。
行政も同じで、1万円の助成金か1000万円の補助金かでは、事前に知りたいことも、期待されることも違います。申請する金額に見合った緻密さ、堅実さと、それを実現する知識・理解が必要です。
つまり、申請する金額が大きくなればなるほど、専門家の力なしに着金にこぎつけるのは難しくなると言えるのです。
補助金・助成金の申請を行う士業とは?
補助金・助成金の申請は、コンサルティング会社等が掲げている場合もありますが、主には士業が支援を行っています。
士業の中でもどのような士業が補助金・助成金に対応しているか、ここでは依頼を検討する場合のヒントを提供します。
行政書士・中小企業診断士が中心に対応
少し詳しい方は、「補助金といえば中小企業診断士」というイメージが大きいかもしれません。
実際に補助金の申請において、現状で中小企業診断士が支援を行っている場合は非常に多いと言えます。
しかし、厳密には補助金の「申請代行」や「申請書類の作成」は行政書士のみができる分野です。
中小企業診断士は、補助金のために限らない一般的な事業計画の作成や、事業者が作成した計画へのアドバイスができるにとどまります。
これまでよりも厳しく判断できるように行政書士法が改正されるため、今後は行政書士が補助金申請支援の中心となるかもしれません。
ただ、行政書士でも経営支援全般を専門とする人はいますが、資格試験の内容からすれば中小企業診断士の方が、経営に関しては専門的な知識を持っています。
申請に直接関係する部分は行政書士に任せるとしても、事業計画について中小企業診断士の意見を聞くのもよいでしょう。
税理士や社会保険労務士が対応するケースも
補助金・助成金の文脈で、税理士・社会保険労務士も関わるケースがあります。どのような場合に関わるのか、それぞれの専門性によって変わってきます。
事業全体のアドバイスができる税理士
お金に関することというところで、税理士も補助金申請に関わることがあります。しかし、中小企業診断士と同様、補助金専用の書類を作成したり、申請そのものを代行したりすることは違法です。
税理士には、補助金のための書類というよりも、補助金を含む事業全体の会計のアドバイスや、資金繰り全般の相談を行うと良いでしょう。
専門の助成金が存在する社会保険労務士
社会保険労務士(社労士)は、他の士業とは少し話が違ってきます。社会保険労務士だけが扱える助成金が存在するからです。
行政書士と社会保険労務士は、「その補助金・助成金が、どの法律に基づいて行われているか」によって棲み分けています。
しかし、一般の方が、補助金・助成金のもとになっている法律を確かめるのは困難です。
ごく簡単な見分け方としては、「厚生労働省が行っている助成金は社会保険労務士」「中小企業庁ベースの補助金は行政書士」と考えるのが良いでしょう。
士業でも全ての補助金に対応できるわけではない
上記で見てきたとおり、すべての士業=補助金・助成金というわけではありません。改めてまとめると、以下のとおりです。
| 士業の種類 | 対応 |
|---|---|
| 行政書士 | 〇原則として補助金全般
〇一部の助成金(主に都道府県・市区町村等が行うもの等) ✕主な助成金(厚生労働省が行うもの等) |
| 社会保険労務士 | 〇助成金(主に厚生労働省が行うもの等)
〇補助金のために限らない一般的な事業計画の作成 〇事業者が作成した計画へのアドバイス ✕(原則)補助金の書類の作成 ✕(原則)補助金の申請代行 |
| 中小企業診断士
税理士 その他の士業 コンサルタント |
〇補助金のために限らない一般的な事業計画の作成
〇事業者が作成した計画へのアドバイス ✕申請代行 ✕提出する補助金・助成金書類の作成 |
もしどの士業に相談するか迷ったときは、どの士業でも良いので「この補助金・助成金を申請したい」と伝えてみてください。
士業同士もお互い紛らわしいことは理解しているので、間違っていれば正しい士業に案内してくれます。
実績のある専門家を見つけるのは難しい
どの士業にも複数の「専門分野」があります。
補助金・助成金を扱うことができる士業であっても、実際に補助金・助成金を専門分野として関わっているかどうかは別の話です。このため、該当の士業であれば誰でも良いというわけにはいきません。
良い専門家に出会うには、補助金・助成金を業務に組み込み、しかも実績がある士業を探す必要があります。しかし、これが意外と難しいのです。
補助金・助成金の種類が多く、得意分野が異なる
補助金・助成金申請を依頼する上での「落とし穴」は、単に「補助金が得意」「助成金申請を受付」という宣伝文句だけでは、どれがどのくらい得意か分からないところです。
世の中には多くの補助金・助成金が存在します。どのような種類の制度を得意としているかは「人それぞれ」ですが、そこまで細かくは掲げていないことも多く、一見して自分が申請したいものに合っているかは分かりません。
また、補助金・助成金は年度によって、制度がガラリと変わることがあります。
実績が公表されていても、「実績のどの部分が、自分に関係した部分なのか?」は、素人にはなかなか判断できないことがあるのです。
表向きに実績を公表していない士業も多い
士業の業務は幅広く、紹介によって営業している人も多いので、実績があっても一般に見える場所では公表していない士業がたくさんいます。
また、補助金・助成金をメイン業務にし、顧客を求めていたとしても、数字では実績を公表していないこともあります。逆に数字を「盛って」、たとえば申請が1件だけで、その1件が採択されたために100%と記載しているようなことも考えられます。
各専門家が公式HPなどで公開している範囲の情報だけでは比較もしにくく、正しいニュアンスをつかむのも難しいでしょう。
ポータルサイトで採択実績の多い専門家を探すのがおすすめ
そんな中、専門家を探す際に役に立つツールの1つが、補助金・助成金に関するポータルサイトです。
ポータルサイトに登録している専門家の中から依頼先を探すメリットは、主に3つです。
まず第1に、ポータルサイトに登録している専門家は、補助金・助成金の業務に注力していることが確実です。膨大な数の専門家の中から補助金・助成金に特化した専門家に絞れるだけでも、大きな効果があります。
第2に、ポータルサイトでは「同じ条件」で専門家を比較することができます。
サイトの登録項目や記載できる長さは限られているため、「デザインで魅せる」「実績の数字を伏せて良く見せる」といった小細工なしの比較が可能です。
第3に、ポータルサイトでは専門家の種類や採択実績で絞り込めます。
サイトの機能を使って、申請したい補助金・助成金や受けたい支援に合わせた検索をし、実績が多い専門家を優先して選べるでしょう。
申請代行を依頼する際の費用と報酬の仕組み
申請支援・申請代行を考える際、最も気になるのが「費用・報酬」です。
これまで専門家の支援を受けたことがない方は、「相談に行ったら高額の請求をされるのでは」「申請しても不採択だったらお金がもったいない」などの不安を感じるかもしれません。
そのような不安は通常、杞憂に終わります。むしろ早めに相談した方が、事業者側の無駄をなくし、低コストで採択に至る可能性もあるのです。
成果報酬が中心なのでリスクが少ない
士業報酬は「着手金」と「成果報酬(成功報酬)」に分かれます。
補助金・助成金の申請に当たっても、本格的な報酬は採択された場合にのみ発生することがほとんどです。もし不採択になっても、着手金のみで済みます。
中には、不採択であった場合、同料金の範囲内や格安で再申請をするという専門家もいるくらいです。
専門家に依頼するメリットはたくさんありますが、リスクはかなり少ないと言えます。
無料相談で「通るかどうか」おおよその見込みを出してもらえる
ほとんどの専門家は「無料相談」を設定しています。
無料相談では、申請したいと考えている補助金・助成金が計画内容に適合しているかどうかや、申請したい内容が審査を通過する見込みがあるかどうかを判別してもらえます。
相談なしに通らない申請をくり返すくらいなら、早めに相談し、どこに課題があるかをハッキリさせるほうが、早くゴールにたどり着くでしょう。
もしかしたら依頼しないかもしれないと思っても、まずは無料相談をしてみるのが早道です。
着手金・成功報酬・受給後サポートの費用例
専門家に依頼した場合の費用例をいくつか紹介します。
| 専門家の種類 | 補助金・助成金の種類 | 補助金額 | 着手金 | 成果報酬 | 事後手続 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政書士 | 補助金 | 50~200万円 | 0円 | 5.5万円 | 5.5万円 |
| 税理士 | 補助金 | 50~200万円 | 5万円 | 10% | 左記に込み |
| 行政書士 | 補助金 | 750~4000万円 | 11万円 | 4.4% | 6.6% |
| 行政書士 | 補助金 | 750~4000万円 | 33万円 | 2%(最低55万円) | 6.6万円 |
| 税理士 | 補助金 | 一律 | 0~15万円 | 5~10% | 顧問契約で対応 |
| 社会保険労務士 | 助成金 | 一律 | 0円 | 15% | – |
| 社会保険労務士 | 助成金 | 一律 | 0円 | 10%~20% | – |
※社会保険労務士扱いの助成金には、原則として事後手続のしくみがありません。
実際の費用を確認する際は、「採択までなのか、事後手続きも含まれるのか」「不採択の場合の再申請の費用はかかるか」もチェックしておきましょう。
補助金・助成金の申請代行を成功させるコツ
専門家に依頼すると言っても、いつでも誰にでも丸投げすれば良いというわけではありません。申請から着金までを首尾よく成功させるには、ちょっとしたコツが要ります。
この記事の最後に、専門家に依頼する際に役に立つポイントをお届けします。
早めに相談してスケジュールを確保する
いくら専門家でも、魔法のように一瞬で申請書類を生み出せるわけではありません。
しかも、自社のことなら「社長が頭の中のことを書きだせば済む」かもしれませんが、専門家ではそうはいきません。これまでの事業の様子から今後の計画まで、大抵は初めて知る内容を聞き取って、まとめ直さなければならないのです。
その分、申請準備には時間が必要です。
ときどき、自社でやろうとしたもののうまくできず、申請期限のギリギリ直前になって専門家を探す方がいます。言うまでもなく、これは得策ではありません。
引き受けてくれる士業が見つからなかったり、なんとか見つかっても採択には至らなかったりします。
専門家に依頼するかどうかは早めに判断し、余裕を持ったスケジュールで依頼しましょう。
実績報告・返還リスクにも対応してくれる専門家を選ぶ
助成金は審査後すぐに着金で終了になる場合も多々ありますが、補助金の場合、「採択」の後にも、そして「着金」の後にまでも、面倒な手続きが盛りだくさんです。
また、補助金・助成金どちらも、手続きに誤りや漏れが発生したり、万が一申請段階で不正があったとみなされたりすると、受け取った後でも返還を命じられる可能性があります。
しかし、採択・受給の後の手続きは、そもそも対応していない専門家や、対応のためには顧問契約が必要とする専門家もいるのが現状です。
あらかじめ対応可否を確認し、これらの手続きとリスクにも対応してくれる専門家を選ぶほうが、申請段階から安心して任せられます。
報酬についても、採択後の手続きを申請時の報酬額に含めるか、別契約とするかは、専門家ごとにさまざまです。依頼する際は、提示された報酬にどこまでの手続きが含まれるか、しっかり確認することをおすすめします。
中には高すぎる報酬を請求する「悪質」と言われるようなコンサルタント・士業も存在し、中小企業庁から苦言を呈されていたこともあります。
依頼を検討する際には複数の専門家を比較し、サービスの内容や実績に合った、全体として納得できる報酬の専門家を選びましょう。
