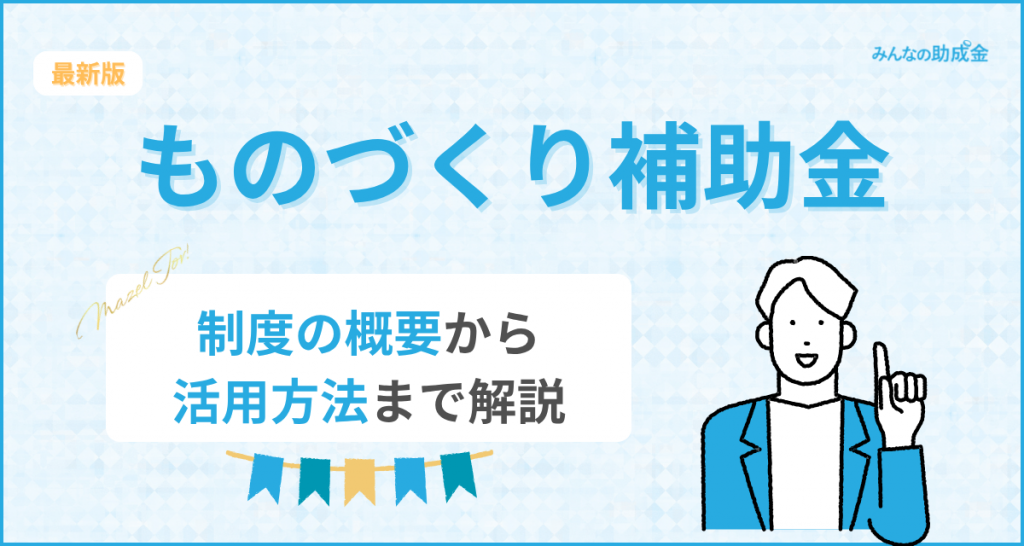
ものづくり補助金は、制度の歴史が古くこれまでに多くの事業者が活用してきました。補助金額が高く、企業の事業支援だけでなく、日本経済を支える重要な制度として活用されています。
「ものづくり補助金は要件や審査が厳しいので活用しにくい」と思っている事業者の方も多くいらっしゃるかと思います。今回は、みんなの助成金編集部が、ものづくり補助金制度の概要と申請方法について解説していきます。
ものづくり補助金にご興味のある方はお気軽にご相談ください。
ものづくり補助金とは
一般に「ものづくり補助金(もの補助)」と呼ばれる補助金は、正式名称を「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といいます。
中小企業や小規模事業者(個人事業主を含む)の設備投資・海外進出を主として、規模や申請枠により、最大数千万円もの補助を受けられます。
二つの申請枠
ものづくり補助金には、現在2つの申請枠が用意されています。それぞれ必要な条件や内容が異なり、向いている事業者さんも違っています。
過去の申請枠とは条件が変わっているところも多いです。新たに申請を検討する場合、必ず最新の申請枠の条件を確認しましょう。
製品・サービス高付加価値化枠
製品・サービス高付加価値化枠は、国内での事業が中心の事業者さんのための枠です。付加価値額や賃金の増加といった「基本要件」を満たしていることが必要になります。
この申請枠では新製品・新サービスの開発が必須です。社内で新しいだけでなく、業界内でも陳腐化していない革新的なものであることが求められます。
この点、過去のものづくり補助金から変更があったところなので、以前にも申請を検討したことがある方は注意してください。
グローバル枠
グローバル枠は、海外向け事業をこれから広げる段階にある事業者さんにぴったりの枠です。
グローバル枠では、「基本要件」に加え、申請する事業が以下の4つのいずれかである必要があります。
- 海外支店・海外子会社など、海外に直接投資する事業
- 輸出に関する事業
- インバウンド需要を獲得する事業
- 海外企業との共同研究開発等の事業
4つのそれぞれで、売上先の割合など、満たさなければいけない条件が異なります。グローバル枠の申請を検討する際は、公募要領や専門家の意見を参考に、要件を満たすかどうか、しっかりと確認してください。
補助対象の事業
ものづくり補助金に申請するには、規模や賃金引上げなどの事業者としての条件を含め、申請する内容が申請枠の要件を満たしていることが必要です。申請枠の説明で挙げた「新製品・サービスを開発すること」などもその1つです。
また、申請する事業を考える上では、対象となる経費をしっかりと把握し、上限の範囲内で補助金額を申請できるような事業にしなければなりません。
対象外の経費を自費で賄う分には問題ありませんが、対象となる経費がなかったり、上限・下限の条件を満たしていなかったりする場合は、入力フォームを完了させることができず、申請ができなくなります。
基本要件
枠にかかわらず必須となる「基本要件」には、次の4つがあります。
- 付加価値額を年平均3%以上増やせる計画
- 従業員と役員、それぞれの給与支給総額が年平均2%以上増やせる計画
- 補助事業を行う事業場内で、時給換算で最も低い給与(事業場内最低賃金)を、都道府県の最低賃金より30円以上高くする計画
- 従業員が21名以上の場合は、次世代育成対策推進法の一般行動計画を作成し、公表すること
これらのうち2と3は、達成できなかった場合、補助金を返還しなければなりません。
もちろん、申請に当たっては、決算書に準ずるような収支計画を入力するコーナーがあるので、そこにこの要件を満たす計画を入力すれば申請できます。
しかし、この要件の肝心なところは、事業を成長させ、利益を出して、その利益を人件費に回せるようになることにあります。人件費を増やす背景には、それを払えるお金ができることが大前提としてあるのです。
要件を守ろうとして人件費に圧迫され、経営が傾いては意味がありません。補助事業を計画する際は、「基本要件を満たす事業を考える」のではなく、「考えている事業で基本要件を満たせるだけの成功を得られるか」の視点が大切です。
対象となる経費
対象となる経費の費目は、機械・システムのほか、外注費、試作品の材料費、海外出張の旅費、知的財産の取得費用などです。
グローバル枠の中で輸出に関連する事業のみ、使える費用項目が多くなっています。
一部の費目には、補助金対象の費用の総額に対する上限割合が定められていることに注意が必要です。
共通の経費は下記のとおりです。
| 経費 | 経費の上限 | 注意点 |
|---|---|---|
| 機械装置・システム構築費 | — | 必ず機械装置・システム等を購入する必要があり、そのうち1つ以上は単価50万円(税抜)以上でなければならない。 |
| 運搬費 | — | 特になし。 |
| 技術導入費 | 補助対象経費総額の3分の1まで | 特許などの知的財産を他社から購入するための費用。 |
| 知的財産等関連経費 | 補助対象経費総額の3分の1まで | 特許取得のための弁理士費用や、外国特許出願のための翻訳費用。 |
| 外注費 | 補助対象経費総額の2分の1まで | 新製品・新サービスの製造等の一部を外注する費用。グローバル枠では海外子会社への外注費が認められる場合がある。 |
| 専門家経費 | 補助対象経費総額の2分の1まで | 技術上の専門家による指導や機械装置のレクチャー費用。相応の専門性が必要で、地位に応じた上限額がある。 |
| クラウドサービス利用費 | — | 特になし。 |
| 試作品の原材料費 | — | 補助事業実施期間内に使い切ること、受払い簿を作成することなど詳細条件あり。 |
海外市場開拓(輸出)条件に該当する場合のみ適用となる条件もあります。
- 海外旅費は上限5分の1まで
- 通訳・翻訳費は上限5分の1まで
- 広告宣伝・販売促進費は上限2分の1まで
事業再構築補助金など一部の補助金では、物件のリフォーム、工事などの費用を補助金申請に含めることができました。店舗改装や新規店舗の準備に活用した方も多いと思います。
しかし、ものづくり補助金では上記のとおり、物件に関する費用が含まれていません。
したがって、もし補助事業のために工事費等が発生する場合には、その費用は全額自費で賄わなければなりません。
補助金額・補助率と対象者の要件
ものづくり補助金を申請できるのは、「中小企業・小規模事業者」に該当する事業者です。
「ものづくり」の名前から「製造業のための補助金」と思っている方もいると思いますが、特に業種の制限はありません。サービス業や小売業なども含め、業態にかかわらず対象になり得る補助金です。
「中小企業・小規模事業者」の定義は業種ごとに、資本金額と雇用人数によって定められています。
補助金の上限額・補助率
ものづくり補助金の補助率は、一般の中小企業は2分の1、小規模企業・小規模事業者は3分の2となっています。また、再生事業者は製品・サービス高付加価値化枠で3分の2です。
ただし、「最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例」を活用すれば、小規模企業・小規模事業者に該当しない中小企業であっても3分の2とすることができます。
補助上限額は枠ごとに異なり、以下のとおりです。
製品・サービス高付加価値化枠
| 従業員数 | 補助上限額 |
|---|---|
| 5人以下 | 750万円 |
| 6~20人 | 1,000万円 |
| 21~50人 | 1,500万円 |
| 51人以上 | 2,500万円 |
グローバル枠は、規模にかかわらず3,000万円です。
さらに、「大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例」を利用すれば、従業員の人数ごとに、以下の額だけ補助上限額を上乗せすることが可能です。
| 従業員数 | 上乗せ金額 |
|---|---|
| 5人以下 | 最大+100万円 |
| 6~20人 | 最大+250万円 |
| 21人以上 | 最大+1,000万円 |
対象となる企業の規模・業種・法人形態
ものづくり補助金は、個人事業、会社のほかに、組合、連合会、NPO法人、社会福祉法人も、要件を満たせば申請することができます。
対象となる中小企業等の規模の定義は、公募要領に表の形式で示されています。業種ごとに掲げられている従業員数と資本金額の条件の、いずれかを満たせば申請可能です。業種に特別な縛りはなく、要件を満たせば、どの業種の事業者さんも申請できます。
なお、従業員数には、アルバイトは含まれ、役員は含まれません。日雇いの人や試用期間中の人は除いてください。また、派遣社員は派遣元の企業の人数に含まれます。
注意すべき「対象外要件」
以下の事業者さんは「対象外要件」に該当し、申請をすることができません。
補助金同士の重複関連
- ものづくり補助金、事業再構築補助金、新事業進出促進補助金のいずれかに16か月以内に採択された事業者、または、これらの補助金の補助事業を実施中の事業者
※まだ採択されていない申請中のものと同時に申請することはできますが、両方が採択された場合、片方を選択しなければなりません。 - 過去にものづくり補助金に採択されて事業を行ったものの、事業化状況報告等の報告を行っていない事業者
- 過去3年間のうちにすでに2回ものづくり補助金を受けている事業者
実質的に中小企業でない
- 大企業に実質的に保有されていると考えられる「みなし大企業」
- 直近3期の平均課税所得額が15億円以上の事業者
- 申請後に中小企業等の条件を満たさなくなった場合、対象外となる
その他
- 親子会社は同一の法人とみなされ、いずれか一方しか申請できない
- 暴力団関係者の申請は不可
2025年ものづくり補助金の公募内容とスケジュール
2025年度のものづくり補助金のうち、第19次公募は4月に、第20次公募は7月に締め切られました。
現在発表されている最新は第21次公募で、締切は2025年10月3日17時です。
例年どおりであればあと1回、年度末締切の公募がある可能性はありますが、確定ではありません。2024年度にはスケジュールに大幅なイレギュラーが発生したこともあります。
申請を考えている方は、第21次に応募しておいた方が良いでしょう。
申請の流れと必要書類
申請にはいくつかの事前準備が必要です。申請までの流れを押さえつつ、必要な書類等について説明します。
中には準備に時間がかかるものもありますので、先に一度目を通しておき、順序立てて取り組むようにしてください。
必要書類の事前準備
全事業者提出
- 直近2期分の決算書/個人は確定申告書
- 法人事業概況説明書/個人は収支内訳書又は青色申告決算書
- 労働者名簿(労働基準法に則った内容のもの)
該当者のみ提出
- 再生事業者に係る確認書:再生事業者の場合
- 大幅な賃上げ特例に係る計画書:特例申請をする場合
- 賃金台帳:最低賃金引上げ特例の申請をする場合
- 金融機関が発行する確認書:金融機関から融資を受けて補助事業を実施する場合
- 申請する事業の市場調査報告書等:グローバル枠の場合
- 経営革新計画、事業継続力強化計画、特定適用事業所該当通知書、株式譲渡契約書など、加点に関する資料
フォームに入力するため、手元に用意する資料
- 事業計画の内容が分かる資料
- 過去に受けた補助金に関する資料
- 次世代育成対策支援法に基づく一般行動計画の掲載URL
労働者名簿
ものづくり補助金では、全事業者が労働者名簿を提出します。
現在のものづくり補助金には、雇用している労働者が1人もいない事業者は申請できません。したがって、必ず1人以上の名簿を提出します。
気をつけなければならないのは、この労働者名簿が「労働基準法の内容を守ったものであること」とされている点です。
本来、言われなくても備えていなくてはいけない書類なのですが、中小企業ではきちんとした名簿が未整備であったり、整備されていると思っても内容が不足していたりすることがあります。
労働者名簿に記載すべき事項は、以下のとおりです。
- 氏名
- 生年月日
- 履歴
- 戸籍上で割り当てられている性別
- 住所
- 業務の種類
- 雇用した年月日
- 退職や死亡をした従業員について、年月日と理由
「履歴」の内容については、特に必須事項はありません。一般的には、異動歴や入社前の経歴を記載する例が多いようです。
提出する労働者名簿はこれらの項目が網羅されたものである必要があり、単に労働者を一覧に書いただけの「名簿」では認められません。この機会に、社内の整備状況も見直しておきましょう。
賃金台帳
賃金台帳も労働者名簿と同じく、本来であれば整備しているはずであるものの、中小企業では抜け漏れが多い書類です。
賃金台帳の記載事項は、下記のとおりです。
- 氏名
- 戸籍上で割り当てられている性別
- 賃金の計算の期間(「〇月1日~〇月31日」など)
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働時間数(残業時間数)
- 深夜労働時間数
- 休日労働時間数
- 基本給や手当の種類と額
- 控除される項目と額
ものづくり補助金では、申請時に賃金台帳が必要になるのは特例申請の場合だけです。
しかし、そもそも賃上げ要件などがあることから、採択後に確認をされることになっても文句は言えません。実際に過去の公募分では、事業実施後の事業化報告の段階で賃金台帳が求められています。
補助金に申請するタイミングで、賃金台帳の整備も見直し、「今だけ」ではない体制づくりをすることをおすすめします。
GビスIDの取得
申請には「GビズID」が必要です。このIDは、国が実施する補助金の申請や雇用保険関係の申請など、複数の手続きで共通して使えます。
IDを取得するには、「GビズID」で検索し、公式サイトから「プライムアカウント」の申請書を作成します。その後、申請書を印刷し、印鑑(個人の場合は実印、法人の場合は法務局に登録されている法人印)を押し、印鑑証明書を添付して郵送します。
ものづくり補助金の申請をすると決めたら、できるだけ早くGビズIDの取得手続きをしましょう。申請書の作成から、郵送後にメールでログインの案内が届くまで、通常1週間程度、最大では2週間ほどもかかるからです。
事業計画書の作成
申請時に添付する事業計画書を作成します。この事業計画書の内容が、審査の上で最も大きな要素になります。
なお、以前は10ページ以内とされていましたが、現在は5ページ以内のPDFとされています。ページ数が少ないため、図や画像を駆使し、より無駄のない資料作成が必須です。
また、現在は社長や従業員の顔写真などを掲載することが「禁止」となりましたので、その点も注意してください。
必要事項を網羅する
事業計画書に必要な事項がすべて記載されていなければ、審査に影響が出るおそれがあります。
特に、以下の内容のうち、電子入力項目だけで伝わりにくい点があれば、間違いなく記載しましょう。
- 申請の大前提となる「基本要件」を満たしていること
- 申請枠ごとの要件を満たしていること
- なぜその項目の製品・サービスが必要なのか
- 購入する製品・サービスによってどのような効率化等の効果が得られるか
- 投資が回収できる見込みの根拠
- その他、公募要領の「事業計画書作成のポイント」に記載されている内容
技術的事項をしっかりと記載
ものづくり補助金では、他の補助金と違い、特に技術的な事項が重視されています。
すなわち、購入する機械等のどのような点が優れた性能であるのか、開発する新製品・新サービスがどんな点で素晴らしいのか、というようなことです。
これらを、顧客側のメリットだけではなく、設計図や性能についての記述を含めて説明します。
ものづくり補助金の申請で求められるのは、見た目の訴求力よりも、根拠が可能な限り数値的にしっかりしていることです。その点を意識してまとめていきましょう。
投資回収の視点を示す
ものづくり補助金では、高額の設備投資を補助するため、「投資した額を生産した商品・サービスで取り返せるのか、取り返すのにどのくらいの期間がかかるのか」を重視します。
したがって、購入する物品によってどれだけ売上が上がるかだけでは足りません。経費も含めた営業利益ベースで、計画する5年程度の間に補助事業の費用を回収し、プラスになる程度の計画が必要です。
申請枠の要件を意識する
それぞれの申請枠ごとの要件を満たしていることを示せなければ、内容がどんなに良くても、審査では落とされてしまいます。
電子申請の入力項目でもある程度は示せるはずですが、不足があると感じる部分はしっかりと計画書に落とし込みましょう。
費用は割引なしで見積もる
計画書の内容には、購入品の金額ももちろん関係してきます。それらの費用は補助金の申請額とも密接にかかわるでしょう。
計画書の作成を含めた事業計画の全体を通じて、費用は「割引を考慮しない」ように気をつけてください。
昨今は常に割引状態になっている通販サイトも多いですし、懇意の業者さんとの間での割引の約束ができている場合もあるでしょう。
しかし、実際の支払額が何らかの理由で申請した額を超えてしまった場合、その部分は自費となり、補助対象になりません。
物価高の折、購入時までに値上がりしてしまうことも考えられます。少なくとも割引はないものとして、少し高めの費用を見積もるくらいでちょうど良いと考えてください。
金額が大きいからこそ、実現可能な計画を
上記のような「コツ」を意識していると、つい売上や利益を「盛って」しまうような、半ば無意識的な過大評価が生じてしまうことがあります。
現実的な範囲で「良い予測」を記入するのは問題ありません。でも、本来は無理な計画なのに、補助金の審査に通るためだけに悪い可能性に目をつぶって書くことは、決しておすすめできません。
そのような計画書で審査を通過して、後で苦労をするのは事業者さん自身です。
補助金はいったん自ら負担した後でなければ支払われません。本当にその金額を負担できるのか、負担した後も事業を伸ばしていく事業体力があるのか、現実を見て計画を立てましょう。もし計画が通りそうもないのであれば、今はまだ、それほど大きな補助金を狙うべき時ではないのかもしれません。
電子申請
ものづくり補助金の申請は電子方式です。公式ホームページの「電子申請」のタブから指定のフォームを開き、入力・書類添付を行って申請します。
GビズIDの準備ができたら、本格的な申請の前に一度申請画面を開き、入力を開始してみると良いでしょう。フォームは途中保存が可能です。項目を事前に確認することで、実際の申請時に落ち着いて対応できます。
また、申請ボタンは早めに押すことをおすすめします。過去、申請締切日の当日に申請システムがサーバーダウンを起こしたことがあるためです。
サーバーダウンとまではいかなくても、急に画面が動きにくくなる、入力した内容がなぜか消えてしまうといったエラーも、申請当日には起こりがちです。締切日には申請者が集中し、システムの負荷が大きくなって、何が起こってもおかしくありません。できるだけ前日までに終わらせるようにしましょう。
ものづくり補助金に関するよくある質問
補助金の申請を考えている方がぶつかるのが、「自分でできるのだろうか」という点です。
ひょっとすると、周囲から「自分は1人でもできた」「専門家は報酬が高くてもったいない」などと言われたことがある方もいるかもしれません。
この記事の最後に、果たして自社での申請が可能なのか、また、専門家に相談することの意義についてもお伝えします。
補助金の申請は自社で行える?
ものづくり補助金の申請を自社で行うことは、不可能ではありません。
ただし、自社で申請するには、IDの取得や申請画面の操作方法とともに、申請を行う事業主自身が、自社の事業について、そして補助金のしくみや流れについても、深い理解を持っていなければいけません。
最悪なのは、自社でできると思って進めてきて、ギリギリになって「やっぱり無理だ」と判明するパターンです。期限直前に引き受けてくれる専門家は少なく、申請自体を断念せざるを得なくなることがあります。
ものづくり補助金は数か月に1回しか公募がないので、一度逃せば事業の実施も3か月遅れてしまいます。「革新的なサービス」や「グローバル展開」のような事業の遅れとして、3か月はかなり大きい時間です。
自分でできるかどうか、少しでも不安や迷いがあるならば、まずは相談だけでも専門家を探して連絡を取り、早い段階から関わりを持っておくほうが良いでしょう。
自社申請と専門家による申請サポートの違い
報酬を払っても専門家に依頼するメリットは、より良い計画を立て、実現することができる点と、面倒な手続きの大半を丸投げできる点にあります。
事業のビジョンや構想を口に出して話し、懸念点を相談すれば、それだけで頭も整理され、補助事業を具体的かつ現実的に進める力になります。専門家はアドバイスをしながら、事業主の頭の中の形のない構想を、補助金事務局が受け取りやすい形式に直してくれます。
そして補助金の手続きは、申請して終わりではありません。採択された後も、たくさんの書類を用意し、数字の整合性をとり、行政からの確認や修正の依頼に応えていかなければ、入金にたどり着けないのです。
とりわけ採択後においては、「設置前・納品時の写真」など、通常の物品購入では作成しない上、後になって作り直すのが難しいようなものもあります。専門家が事前に指示してくれれば、逃してしまって困ることもありません。
ただでさえ補助事業の実施で忙しいときに、書類仕事や行政とのやりとりまで漏れなくこなすのは大変です。専門家は間に入って行政の言葉を「通訳」したり、代わりに書類を作ってくれたりします。
自社で申請をすることはできるかもしれませんが、長期的に見れば、専門家がサポートに入っているほうが、補助事業全体が効率よく、成功路線で、ラクに進められると言えるでしょう。
ものづくり補助金はいつ入金される?
「補助金に採択されたから、すぐにでもお金が入るはずだ」。そんな風に勘違いする人が後を絶ちません。
補助金が入金されるのは、事業を実施し、その証拠を提出して、審査された後のことです。補助事業の実施期間は最大で採択発表日から12か月(グローバル枠は14か月)ですから、入金は申請時点から見て、最大で1年半ほども先になる可能性があります。
補助事業に必要な費用の全額を、いったんは自社で負担しなければならないこと。その上で、入金を待ちながらも事業を運営し、成長させて、人件費を増やさなければならないこと。この2つを忘れないでください。
専門家であれば、この間をつなぐための資金繰りについても相談できます。入金を待つ間に倒れてしまうことがないよう、早めの相談がおすすめです。
