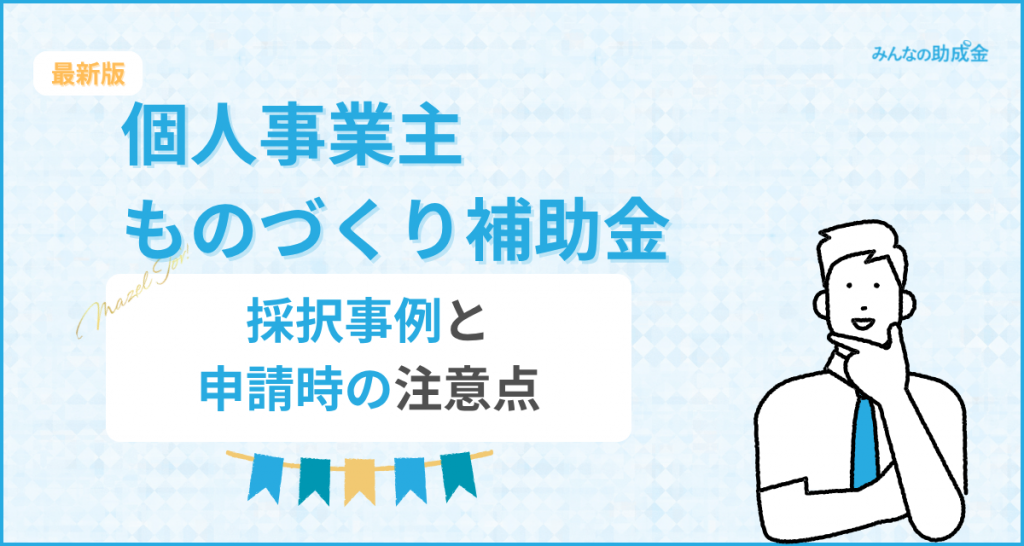
ものづくり補助金は金額が大きく、個人事業主も申請できるのか不安に思う方が多いようです。
この記事では、個人事業主がものづくり補助金に申請することができる条件や、実際の採択事例、注意点などについて解説します。
ものづくり補助金は個人事業主も対象
ものづくり補助金は、「中小企業・小規模事業者(中小企業等)」を対象にした補助金です。
「中小企業等」の記載のせいで「個人事業主は企業ではないから、対象外」と考えている方も見かけます。しかし、条件を満たしていれば、個人事業主でも申請することは可能です。
個人事業主が対象となる条件
対象となる「中小企業等」の規模の範囲は、業種ごとに資本金額と従業員数で決められています。個人事業主は資本金の概念がないため、従業員数のみで判断します。
| 業種 | 従業員数 | |
| 製造業、建設業、運輸業、旅行業、その他 | 300人以下 | |
| ゴム製品製造業(ただし、自動車・航空機用のタイヤ・チューブ、工業用ベルト製造業は上段) | 900人以下 | |
| 卸売業 | 100人以下 | |
| サービス業 | 100人以下 | |
| ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 300人以下 | |
| 旅館業 | 200人以下 | |
| 小売業 | 50人以下 | |
また、「小規模事業者」として補助率などで優遇があるものは、以下のとおりです。
| 業種 | 従業員数 | |
| 製造業、その他 | 20人以下 | |
| 商業・サービス業 | 5人以下 | |
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 | |
従業員を雇用していること
ものづくり補助金では、1人でも従業員を雇用していないと、申請自体をすることができません。
従業員数を数える際のポイントは以下のとおりです。
| 従業員数に含む | 従業員数からは除く |
| ・いわゆる正社員
・アルバイト、パート ・他社に派遣している派遣社員、派遣バイト |
・事業主本人
・家族従業員(いわゆる専従者) ・受け入れている派遣社員、派遣バイト ・試用期間中の人 ・日雇の人 ・業務委託の人 |
確定申告をしていること
ものづくり補助金では、必須提出書類の中に確定申告書が含まれます。
提出する確定申告書には事業所得が計上されていなければなりません。ときどき所得の種類を誤っている方がいますので、事前に確認してください。
白色の場合は収支内訳書、青色の場合は青色申告決算書もあわせて必要です。
なお、創業から間もなく、確定申告の提出時期を経過していない場合は、「(補助事業だけでない)事業全体の計画書及び収支予算書」が必要です。これには決まった様式がないので、必要なときは早めに専門家に相談したほうが良いでしょう。
開業届の提出があること
ものづくり補助金の申請にあたり、開業届の提出は必須ではなくなりました。
しかし、採択後に求められることは十分に考えられます。
開業届を出す手続き自体は簡単です。提出していなければ、申請前に提出しましょう。
届出はしたが控えをなくしてしまった、という場合は、以下の方法で入手できます。
- 申告書等閲覧サービス
税務署で書類を見せてもらい、撮影できます。ただし、現場の判断で撮影範囲が制限されることがあります。 - 保有個人情報開示請求
写しを入手できますが、2週間~1か月程度かかります。 - 再提出
開業届の二重提出は禁止されていません。再度提出すれば控えが手に入ります。ただし、開業日と受付日が大きく離れ、不信感を持たれる場合もあります。
個人事業主の補助額と支援内容
ものづくり補助金では、個人事業主であっても、法人と同様の条件で補助率・補助上限額が決まります。しかし、個人事業ならではの事情から、個人事業主の申請規模には一定の特徴が見られます。
実際の事例をもとにしながら、個人事業主の申請について詳細を見ていきます。
補助金額の上限と補助率
ものづくり補助金の補助率は、通常2分の1(小規模事業者に該当する場合は3分の2)です。
「最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例」を利用すれば、小規模事業者に当てはまらない事業者も補助率を3分の2にすることができます。
補助上限額は従業員数に応じ、以下のとおりです。
| 製品・サービス高付加価値化枠 | 従業員数 | 上限額 |
| 5人以下 | 750万円 | |
| 6~20人 | 1,000万円 | |
| 21~50人 | 1,500万円 | |
| 51人以上 | 2,500万円 | |
| グローバル枠 | 一律 | 3,000万円 |
個人事業主に多い申請規模
ものづくり補助金の申請においては、法人よりも個人事業主のほうが、規模や売上などの条件が千差万別で、申請額も二極化しやすい傾向があります。
以下では、200万円程度で採択される事例と、1,000万円程度で採択される事例を見てみます。
200万円前後で採択されるケース
小規模な事業を営む個人事業主では、補助額200万円程度(補助率が3分の2であれば、実費用は300万円+税額程度)が、現実的に無理のない計画と言えます。
菓子店が包餡機を導入し、人の手では作れない繊細な新製品の販売を開始した事例や、パンの販売店がパンの種類を見分けるレジシステムを導入して効率化を図った事例があります。
この規模の申請では、必要な機材・システムを厳しく見極める必要があります。「あれも、これも」ではなく、ピンポイントで1点か2点をメインに据えて考えましょう。
高額案件(1000万円規模)の事例
1,000万円程度(実費用1,500~2,000万円+税程度)での採択は、グローバル枠での採択を除けば、個人事業主では高額なほうと言えます。
個人事業主の中でもある程度の規模がある事業者や、もともと高額機材の利用が多い、工業的な処理を伴う業種の事業者が多くなります。
この規模の申請では、高額機材・システムを複数含め、相互に関連させて、全体の効率化やまったく新しいサービスの提供を図ることができます。
たとえば、クリーニング店が一連の機器を一新した事例や、畳店が自動化のための複数の機器・ソフトウェアを導入し、生産性を2倍にした事例があります。
個人事業主の採択事例
「どんな設備・計画なら採択されるのか分からない」「自分の業種では、どんな事例があるのだろうか」。個人事業主の事例が身近にない方が多いからこそ、悩む方も多いと思います。
過去の採択事例を業種別に紹介します。
製造業での活用事例
製造業はものづくり補助金の趣旨とも相性が良いことから、多くの採択事例があります。
- 食品製造業者が冷凍システムを導入し、食材を長期保存して計画的な製造が可能になった
- 理論上はもっと速くできるはずだが、手元の機械の特性により実現できずにいた金属加工業者。最新機器の導入で理論値を実現し、リードタイム40分→10分へ
- アパレル製造業者がCAD/CAMを導入。労働者の身体的負担を軽減しつつ、生産キャパシティーもUP
サービス業での活用事例
一見してものづくりや機械・システムとの関連性が低く思えるサービス業でも、ものづくり補助金の活用事例があります。
- バッティングセンターが最新式のピッチングマシンとキャッシュレス化装置を導入し、サービスの満足度を大幅UP
- 地方新聞の発行者が印刷関連の機器を一新。データから印刷新聞の完成までの時間を4時間30分も短縮し、内容の充実に時間を割けるようになった
小売・飲食業での活用事例
顧客単価が低めの小売業や飲食業でも、ものづくり補助金に採択され、成功した事例があります。
- 花の販売店が鮮温庫を最新のものにし、商品を長持ちさせて廃棄や仕入頻度を減らせた
- 消費期限の短い食品を販売している事業者が、急速冷凍設備で通信販売できるようになった
個人事業主がものづくり補助金を申請する際の注意点
審査の上での区別がなくても、実態として個人事業主と法人では違っている点も多く存在しています。
個人事業だからこその事情を踏まえつつ、少しでも採択に近づけるよう、ものづくり補助金申請時の注意点をまとめます。
法人との違い(審査で不利になる点)
個人事業と法人の間にある制度的な違いの中には、審査段階で不利になりがちな点がいくつかあります。
以下では、どのような不利になり得る点があり、また、どうすればその不利を回避することができるのかをまとめました。
資本金がない
個人事業には、会社のような「資本金」という概念がありません。
会社では資本金額に応じて信用力が高まり、融資なども受けやすくなります。また、法人では、別の出資者が出資を追加することができます。
個人事業に資本金がないということは、信用力を証明できるものが少ないということであり、事業主個人の資本が尽きたら事業も終わる可能性が高いということです。
このため個人事業の場合、「万が一」の救済措置がやや少なく見積もられます。
申請にあたっては、資金面での説得力を高める必要があります。十分な資金があり、将来的にも不足のない売上が見込めることや、すでに融資のめどが立っていることなどを、しっかりと説明しましょう。
事業体力が低い場合が多い
個人事業では法人に比べ、手持ち資金や動かせる従業員の数など、補助事業を実施する上での「体力」が低いことが多いでしょう。
このような小規模の事業者からの申請で見られるのは、「本当にこの事業者は、計画内容を実施できるのか?」ということです。
事業が小規模であればあるほど、現実的で具体的な計画を立て、審査担当者に「これだけしっかり考えているなら、できるだろう」と思わせなければなりません。
継続力が低い
法人は構成員をすげ替えれば、原理的には永遠に続けられる機関です。バトンタッチを容易にするしくみもたくさんあります。
個人事業は事業が代表者本人と強く結びつき、法人のようにスムーズにじわじわとバトンタッチを進めるようにできていません。
そこで、事業主が高齢であったり、事業に関わっている人が少なかったりする場合には、「1人で今後も続けられるのだろうか?」「後継者のめどはついているの?」と不安が生まれてしまいます。
個人事業主の申請時は、後継者の候補がいることや、事業が多くの協力者に支えられていることを示すと印象が良くなります。できれば具体的な氏名を挙げるのが良いでしょう。
よくある不採択パターン
不利になりやすい条件もあることから、「個人事業主の申請は通りにくい」というようなイメージを持っている方が多いかもしれません。
しかし、ありがちな不採択パターンを理解し、回避するようにすれば、個人事業主であっても採択される可能性は十分にあります。
事業計画が具体性に欠ける
過去の成功事例に触れた結果、成功事例をまねれば採択されると考え、無理な計画を立ててしまう事業者さんがいます。
しかし、まねをして立てた計画は、規模や資金の面で実現可能性が見えなかったり、具体的な手順があいまいであったり、これまでの事業との結びつきが薄かったりします。たくさんの事業計画を見ている審査担当者からはそんな実体のなさが「バレバレ」で、不採択になってしまいます。
他社の事例はあくまでも「参考」にとどめましょう。これまで取り組んできた、よく知っている事業をベースに、具体的で実行可能な計画を立てるのが採択の近道です。
補助対象外の経費を計上している
補助対象外の経費を補助金申請額に計上して不採択になる事例は、非常に多いと言えます。
これを避けるため、重要なポイントは2つあります。
1つは、補助対象経費の範囲について、漏れなく把握することです。公募要領では表だけではなく、他の部分や小さな注意書きにも、対象外経費について触れている部分があります。読みこなせないときは専門家を頼りましょう。
もう1つのポイントは、補助対象外経費が発生する場合の明記です。
事業計画に説得力を持たせるために販促やリフォームについて触れるなど、補助対象外経費について言及するのは構いません。ただその際は必ず、①補助対象外経費であると認識していること、②その費用については自費で負担する(できる)こと、この2点を明記してください。
他の給付金・補助金との併用制限
これまでに給付金・補助金を受けたことがある場合、ものづくり補助金も申請できるかどうか、不安に思うかもしれません。
「給付金」は、補助金と併用できます。通常、給付金は単に条件を満たせばお金をもらえるもので、使い道の制限をしていないためです。
では補助金はどうでしょうか?ものづくり補助金の具体的な併用制限を見てみます。
同時に2つはできない
①事業再構築補助金、②新事業進出促進補助金、③ものづくり補助金の補助事業を実施中の事業者は、新たにものづくり補助金に申請することができません。
「補助事業を実施中」とは、採択後、実績報告までの間にあって、辞退していないものです。
上記の3つの補助金に「16か月以内に採択された場合(辞退済みの場合は除く)」も、新たな申請はできません。また、これらの補助金の申請中にものづくり補助金を申請をすることはできますが、両方とも採択されたときは、どちらか一方を選択します。
上記以外の補助金(都道府県・市区町村の補助金など)については、ものづくり補助金の側では制限されていません。しかし、他の補助金の側で、ものづくり補助金との併用を認めていない場合があります。2つ以上の補助金に申請したいときは、両方のルールを確認しましょう。
ものづくり補助金の「おかわり」制限
ものづくり補助金は、2回以上受け取ることも可能です。
ただし、以下のような場合は申請できません。
- 16か月以内にものづくり補助金に採択されている場合(辞退したときを除く)
- 過去のものづくり補助金で事業を実施したが、「事業化状況・知的財産権等報告書」の提出をしていない場合
- 過去3年の間にすでに2回のものづくり補助金の交付決定を受けた場合
申請不可ではないが減点される場合も
申請できない条件に当てはまらない限り、2回目以降の補助金申請も可能です。ただし、2回目以降では「減点」され、より厳しい審査になることがあります。
減点されるのは、以下の場合です。
- 過去3年間にものづくり補助金の交付決定を1回以上受けたことがある場合
- ものづくり補助金に採択されて事業を行ったものの、給与支給総額や最低賃金の目標を達成できなかった場合
- ものづくり補助金、事業再構築補助金、その他中小企業庁が行う補助金で、賃金引上げの加点申請をしたが達成できなかった報告から18か月以内である場合(災害等によりやむを得なかった場合は除く)
- 事業再構築補助金、新事業進出促進補助金、ものづくり補助金を受けたことがあって、直近の事業化状況報告の事業化段階が3段階以下の場合
2点目以降の減点措置は過去の成績が悪かった場合です。
計画が実現可能なものであり、かつ、手続きを怠らなければ、減点措置は防げます。すでに採択されたものがあるときは、必要に応じ専門家の手も借りながら、まずは適切に完了させることに注力しましょう。
