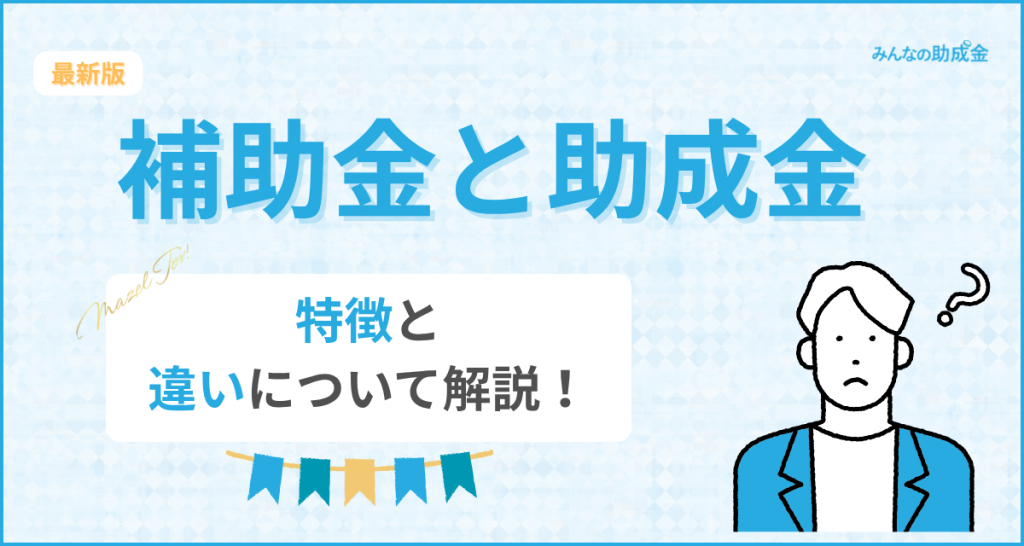
補助金と助成金は、同列に語られることもあれば、異なるものとして語られることもあります。
実際に「補助金」と「助成金」の2つの言葉は混同されがちです。また、両方の要素をあわせ持った中間的な制度も存在しています。
補助金と助成金の違い
国の制度を中心とした原則的な分け方をベースにして、補助金と助成金がそれぞれどんなものと言えるかを見ていきましょう。
補助金
補助金はその名の通り、特定の事業を「補助」します。
事業者の「挑戦したいが金銭的な不安がある事業」と国の政策の方向性が合致する場合に、その事業の費用の一部を補助し、金銭的な負担を減らそうとするものです。
補助額は制度によりさまざまですが、多くは百万円以上、場合によっては数千万円規模まで存在します。
通常、補助金を使って行う内容は、それ自体で利益が上がる可能性がある事業的取り組みです。設備を刷新して効率化する、新しい事業を始めて経営を立て直す、広告宣伝を行って顧客を拡大するなどがあります。
このような事業的な取り組みの内容や効果は、事業者によって大きく違ってきます。国としては、できるだけ良い事業に効率よく「投資」したいところです。
そこで補助金では、一部の例外を除き、他の事業者と比較するプロセスを経て、誰に補助金を渡すか選び出すものが多くなっています。
また、具体的な出費に対して補助をするため、利用できる費目が決まっていて、あらかじめ何を購入するかを伝える方式です。
補助金は、国においては中小企業庁が主に行っています。
ただし、各補助金の事務局は通常の行政機関の窓口とは別に設置され、一部の補助金ではその運営が民間事業者に委託されていることもあります。
助成金
助成金は、国や行政が奨励する内容を事業者が実行した場合に金銭を支給するものです。金額は数十万円程度が一般的です。
東京都など地方自治体では、同様のしくみのものを「奨励金」と称していることもあります。
助成金の対象となるのは「国がお金を出してでもやってもらいたいこと」であり、「お金を出さなければなかなかやってもらえない、直接の収入にならないこと」でもあります。
例えば、雇い手が少ない属性の人を雇ったり、雇用に関する社内制度を改善したり、働く人の収入を増やしたりといったことです。
助成金は行う内容に事業者ごとの差が出にくいため、特に比較はせず、条件を満たしさえすれば支給されることが多いのも特徴です。
ただし、予算が尽きたことを理由に早期に締め切られることはあります。
具体的な費目の申請が必要な場合もありますが、多くは費目を限らず、条件を満たすだけで一律に支給されます。
国では、雇用に関する改善を担う厚生労働省が、さまざまな助成金を実施しています。ハローワークや労働局などの行政機関の常設の窓口が、直接担当していることが多いです。
補助金と助成金の共通点と相違点
補助金と助成金、それぞれの説明をもとに、共通点と相違点をまとめてみます。
| ポイント | 補助金 | 助成金 |
|---|---|---|
| 内容の事業性・収益性 | あり | なし |
| 具体的な使い道(費目) | 必要 | 不要のことが多い |
| 金額 | 数十万円~数千万円以上 | 数万円~数百万円程度 |
| 他の事業者との競争性 | アリが多い | ナシが多い |
| 主な取り扱い省庁 | 中小企業庁 | 厚生労働省 |
| 運営・事務 | 専門の事務局設置 | 行政機関の窓口 |
必ずとは言えないのが難しいところではありますが、一般に補助金は「競争を経て選ばれた事業のうち、一定の費目に使ったお金の一部を補助するもの」と言えます。
これに対し助成金は「国や行政がやってほしいと思っていることを推進するために、条件を満たす取り組みをした事業者に決まった額を支給するもの」との理解が一般的です。
補助金の特徴と代表的な制度
ここからは、具体的な補助金制度を見ながら、補助金の特徴を捉えていきます。
現在、国が行っている主な補助金として、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金の3つを掲げました。共通点、相違点を見ていきます。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、補助額50万円を標準とする、例外的に小さな補助金です。
最大でも200万円程度のため、大きな設備には使いにくい反面、小回りが利きます。小さめの機材や、チラシ・ポスター・展示会などのリアル集客ツールにおすすめです。
補助金制度の原則にならい、競争制で、特定の費目に使った費用が補助されます。金額が小さいこと以外は、ごく一般的な補助金のしくみと言えます。
ものづくり補助金
ものづくり補助金(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)では、条件により750万~4000万円の補助が行われます。
単価50万円以上の機械・装置を必須としているため、高額な機材を要する事業の方におすすめです。
中小企業庁によるもので、補助対象の事業者は競争によって選ばれ、専門の事務局が対応しています。金額的にも制度的にも、モデル的な内容の補助金です。
IT導入補助金
IT導入補助金は、同じ中小企業庁によるものですが、国の補助金の中ではかなり変わった制度構造になっています。
まず、ここまでに挙げた2つと異なり、競争がありません。不採択のシステムはあるものの、他の事業者と比べてどうかではなく、要件を満たしているかがポイントになっています。商品の販売事業者が申請に関わるしくみも、他とは大きく違っています。
あらかじめ対象となる「商品」がリスト化されたカタログ方式が採用されているのも、補助金の中ではどちらかといえば珍しいと言えます。
実際にかかった費用の一部が補助される方式である点と、専門の事務局が設置されている点では、補助金らしさが感じられます。
助成金の特徴と代表的な制度
続いて、有名な助成金の制度をいくつか見て、補助金との違いを明らかにしていきます。
ここで取り上げるキャリアアップ助成金、両立支援助成金、業務改善助成金は、いずれも厚生労働省が行っているものです。特にキャリアアップ助成金は、聞いたことがある方も多いことでしょう。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、個別の雇用と社内の雇用関係制度に関するさまざまなステップアップを奨励し、実践した事業者に一定額を支給するものです。非正規雇用から正規雇用へ、社会保険適用外から適用へ、などがあります。
申請のコースや金額の算定方法が複雑なため、一概にいくらもらえるとは言えません。しかし、通常は人数や加算も加味して、少なくとも数十万円程度を受け取るように、取り組み内容を調整する場合が多いと考えられます。
この助成金は、競争がある補助金とは違い、条件を満たし、期間内にきちんと手続きを踏めば、必ずもらえます。
振り込まれる助成金は必ずしも何らかの費用に対するものと明記されているわけではありません。したがって、何にいくら使ったか、詳細な会計報告は不要です。
ただ実際には、条件を満たすための取り組みに費用がかかるため、「単にお金が増える」ことにはなりません。また、賃金台帳など雇用に関するお金の報告は行うことになります。
両立支援助成金
両立支援助成金は、育児・介護・不妊治療などをしやすくするような体制整備をしたり、適切に休業させたりした事業者に支給される助成金です。
それ自体で収益になるような内容ではなく、むしろ事業者にとっては負担にもなるような内容を条件としている点で、キャリアアップ助成金と並んで典型的な助成金と言えます。
詳細な費目の指定がないこと、しかし取り組みのために費用・手間がかかるため結果として費用補助の性格になる点も、キャリアアップ助成金と変わりません。
厚生労働省はこのようなしくみの助成金を他にも多く出しています。
業務改善助成金
上の2つに対し、業務改善助成金は補助金的な要素が強い、珍しい助成金です。
生産性向上に関する設備投資を条件とし、詳細な費用と効果の報告を求めている点、特定の費目に対する補助の形で支給される点は、非常に補助金的と言えます。
一方で、それと同時に賃金の引上げを条件に加え、上限額も引上げ人数に応じて決まる点は助成金的です。他の事業者との競争もありません。
国の制度としては他に類を見ないタイプの助成金であり、申請を行うには「雇用関係制度」と「経営」、両方の専門性が必要です。
補助金と助成金を活用する際の注意点
ここまで、補助金と助成金の主な違いや、一般的な制度内容について見てきました。補助金と助成金の中間のような制度もあるものの、全体的な傾向としては、それぞれどのようなものを指すかが見えてきたのではないでしょうか。
最後に、実際の申請を検討するにあたっての注意点をお伝えします。
名称だけで判断しない
最初にも少し触れたとおり、「補助金」「助成金」という言葉が使われていても、両方の要素を持っていたり、少し変わった内容が含まれていたりします。
名前だけで内容を判断せず、公表されている要領に目を通す、専門家に相談するなど、実際の条件を確認することが大切です。
負担なしでお金がもらえるわけではない
補助金にも助成金にも共通して言えるのは、「負担なしでお金がもらえるわけではない」ということです。
補助事業や助成金に伴う制度整備では、物品やシステムの購入、専門家への依頼などに費用がかかるだけでなく、維持管理の費用が発生する可能性もあります。
賃上げや正社員化は、当座の費用は少なく見えるかもしれません。しかし、いったん上げた雇用条件を戻すのは難しいため、今後ずっと費用がかかり続けるのです。
補助金であろうと助成金であろうと、目先の補助額・助成額に囚われるのではなく、現実の自社ができる範囲で考えることが大切です。せっかく取り組んでも、完遂できなければお金がもらえないこともあります。
本来の事業は自力で頑張りつつ、「ちょっとの背伸び」や「イメージアップ」のために自社に合った制度を探し、利用する。それが補助金・助成金活用の成功の秘訣です。
