
超高齢化に伴って認知症のある人は今後も増加を続けると予測され、その対策はわが国の公衆衛生上重要な議題です。現時点では簡便かつ侵襲性の低い客観的診断方法が無く、鑑別診断も困難であり、治療・予防法等、十分に確立・標準化がなされていません。そこで本事業は、「実態把握」、「予防」、「診断」、「治療」、「ケア」等について、それぞれに重点的な研究を推進しています。

超高齢化に伴って認知症のある人は今後も増加を続けると予測され、その対策はわが国の公衆衛生上重要な議題です。現時点では簡便かつ侵襲性の低い客観的診断方法が無く、鑑別診断も困難であり、治療・予防法等、十分に確立・標準化がなされていません。そこで本事業は、「実態把握」、「予防」、「診断」、「治療」、「ケア」等について、それぞれに重点的な研究を推進しています。

日本万国博覧会記念基金事業は、1970 年に開催された日本万国博覧会の成功を記念し、万博の収益金の一部を基金として管理し、その
運用益を万博の成功を記念するにふさわしい国際相互理解の促進に資する活動を対象に、1971年から累計で約 4,500 件の事業に対して約 192 億円の助成金を交付しています。

草の根技術協力事業は、国際協力の意志のある日本の NGO/CSO、地方自治体、大学、民間企業等の団体が、これまでの活動を通じて蓄積した知見や経験に基づいて提案する国際協力活動を、JICA が提案団体に業務委託して団体との協力関係のもとに実施する共同事業です。
草の根パートナー型(以下、パートナー型)は、開発途上国への支援において既に豊富な経験と実績を有している NGO 等の団体を対象とした事業形態です。
パートナー型の事業実施を通じて提案団体のこれまでの経験や強みを活かし、より開発途上国の課題解決に寄与する事業を展開することが期待されています。
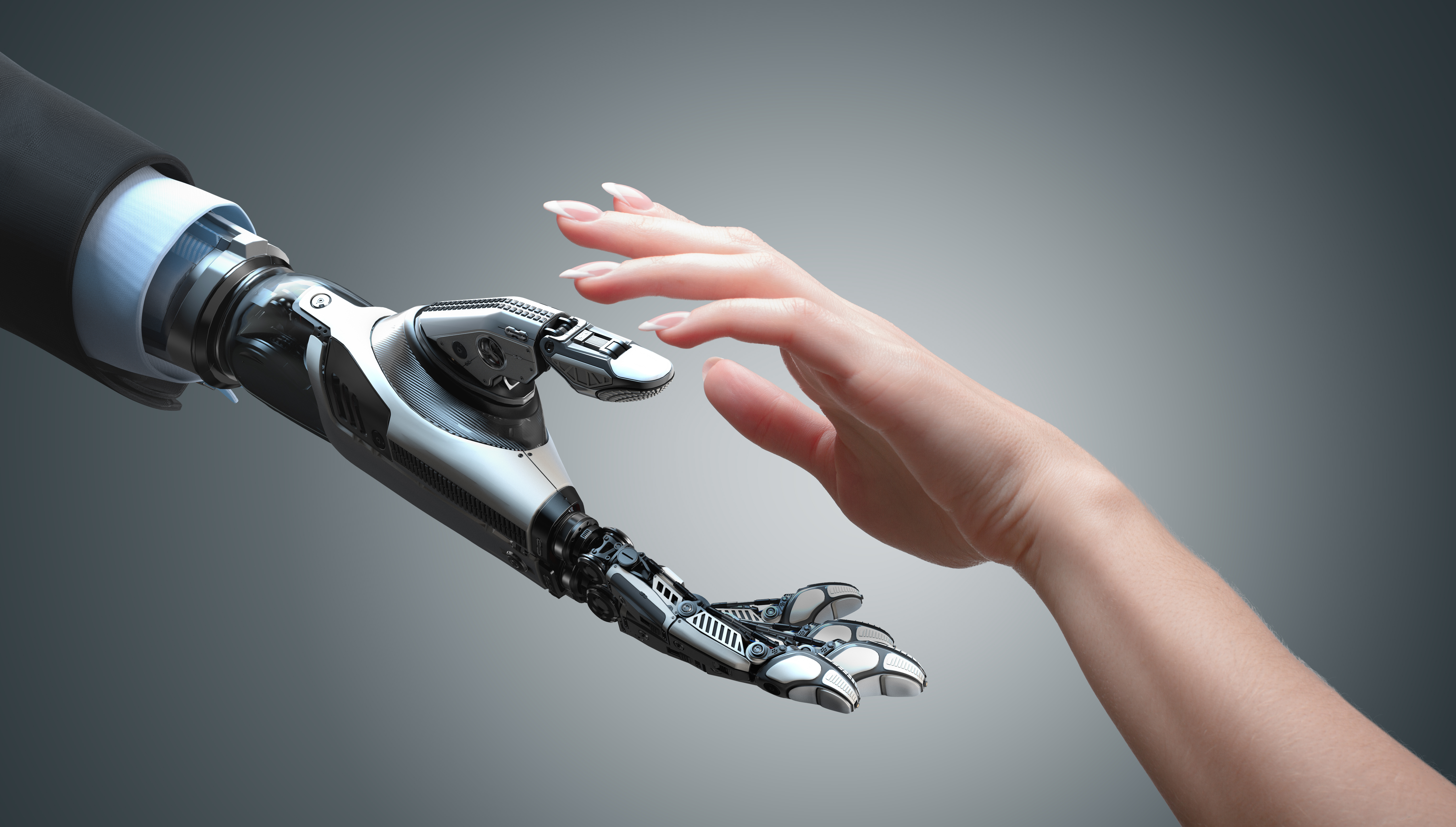
新たな技術を活用した介護ロボットは市場化されて間もない状況にあるものが多く、また価格が高額であることなどを踏まえ、愛媛県では、介護ロボットの使用による介護職員の負担の軽減と働きやすい職場環境の整備を図ることにより、介護職員の確保に資するよう、先駆的な介護ロボットを導入する県内の介護サービス事業者に対し、経費の一部を補助します。

難病の子どもとその家族は、重い障害やつらい治療に負けず今日も病気とたたかいつづけています。どんなに重い病気でも、どんな障害でも子どもは日々、成長・発達しています。そして、そうした子どもたちや家族を支えたい、力になりたい、明日への希望と勇気になりたいという思いで、この助成金ができました。難病の子どもたちとその家族に対して、社会医学的な実践、セルフヘルプ活動、又はボランティア活動を進めている団体の活動をこの助成金でサポートしていきたいと思います

この度、子どもの貧困問題の解決に取り組むため、子ども社会に格差のない「平等の機会」を与えようと地域で頑張る「子ども食堂」を支援することを目的とした『JM 基金』の募集を開始いたしました。

活力あふれる長寿社会を実現するため、「高齢者の福祉向上あるいは健康の維持・増進を目的とした実践的な調査・研究」に対して助成します。また、高齢者の多様なニーズに沿った「分野横断的な調査・研究」や福祉現場からの「実践的な創意工夫の調査・研究」についての応募も募集します。

大阪産業振興機構では、大阪府内のものづくり中小企業を支援するため、リード エグジビション ジャパン株式会社が主催する第9回 ヘルスケア・医療機器 開発展 大阪【MEDIX OSAKA】に大阪産業振興機構ブースを出展します。財団ブース内に、自社製作の医療関連機器または医療関連機器部品を展示する「共同出展企業」を募集します。

大和ハウスグループでは、「共創共生」をキーワードに、全国各地で地域社会に密着した社会貢献活動を実施しています。その中で、従業員が気軽に参加できる社会貢献活動として「大和ハウスグループ エンドレス募金」を運営しています。
従業員の任意により毎月の給与の一部を募金に充て、社会的課題の解決に向けた団体に寄付を行うプログラムです。社会的課題の解決に取り組む団体の活動内容や弊社へのご要望をお聞きするため、2015年度より支援先団体を公募し、書類審査および従業員の投票を経て支援先の選定を行っています。

公益財団法人 京都オムロン地域協力基金(オムロン基金)は、様々な事情から食事の問題を抱える子どもたちやその保護者等のために、子ども食堂を開設または運営するための費用の一部を助成します。
京都府や京都市などから子ども食堂の開設および運営費用に対する補助金や助成金を受給している、または受給予定である子ども食堂もオムロン基金の助成制度に申し込むことができます。