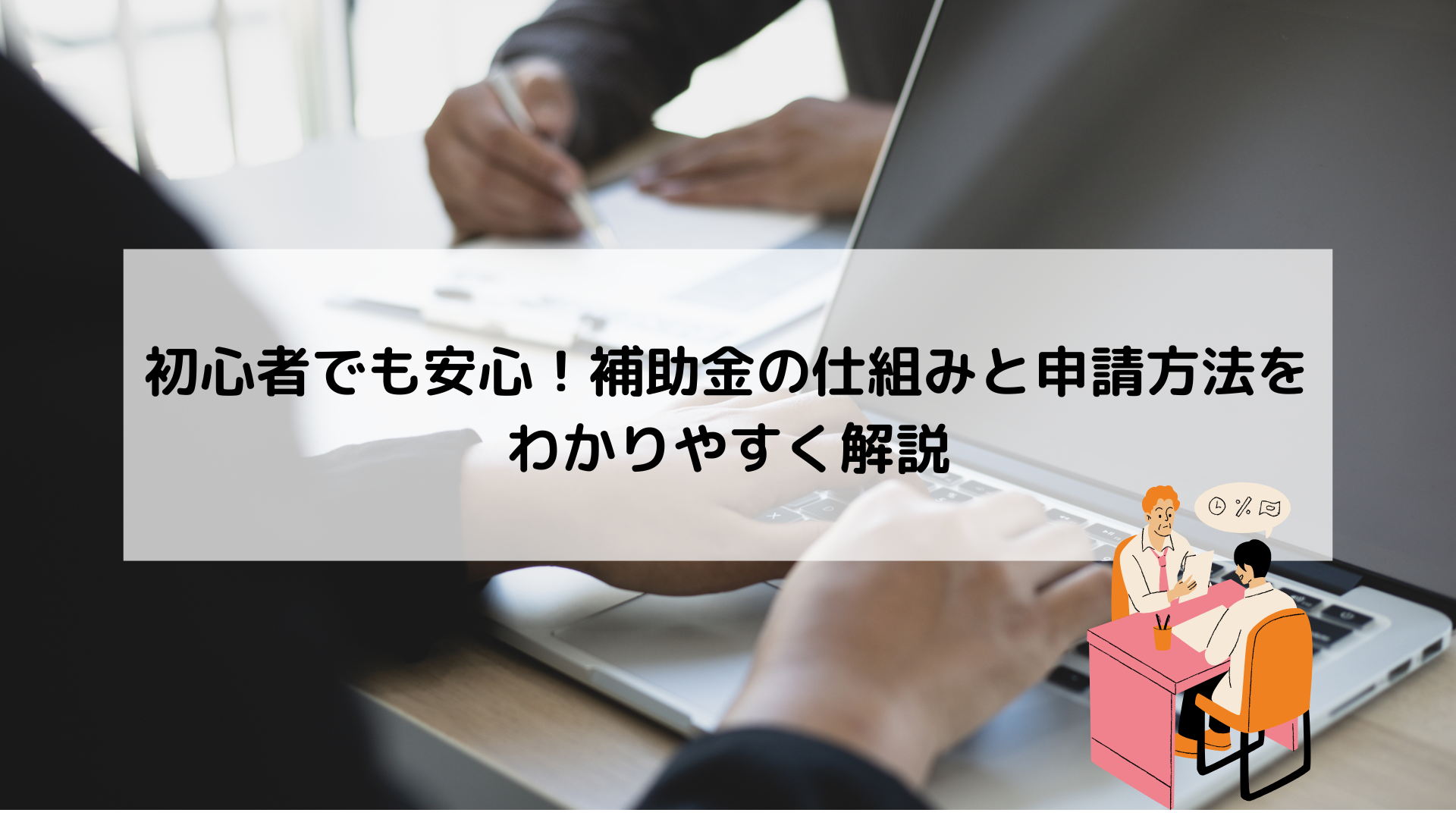
補助金は、国や自治体が企業の事業拡大や新規事業を資金面からサポートする制度です。
しかし、補助金には様々な種類があり、補助対象や申請方法などが異なるなど、複雑になっているのが現状です。
本記事では補助金の基本的な仕組みや申請方法についてわかりやすく説明します。
1補助金とは
1-1補助金とは?
補助金とは、国や自治体が、人手不足解消のための設備投資やシステム導入といった公益性が認められた事業者の取り組みを金銭的に支援する制度です。
補助金の目的や対象となる事業によって、補助金額や補助率、申請方法が異なります。
補助金を上手に活用すれば、事業の成長や会社の業績に大きな影響を与えることもあるため、資金調達の手段の一つとして検討する価値があります。
1-2補助金活用のメリット・デメリット
補助金を活用することで、事業にさまざまなメリットが期待できる一方で、いくつかのデメリットもあります。
| メリット | デメリット |
| ・事業の成長を加速 ・資金調達の支援 ・事業計画の見直し機会 |
・申請の手間と時間 ・不採択のリスク ・報告義務の負担 |
特に助成金や給付金とは異なり、要件を満たせばとか、申請すれば補助金が必ずもらえる、というものではないので注意が必要です。
2補助金を受け取るまで
2-1補助金について知る
補助金には多くの種類があり、応募条件や補助対象、実施期間がそれぞれ異なるため、これから取り組む事業に適した補助金を見つけて、効果的に活用することが大切です。
例えば、コロナの影響で売上が減少した事業者が、新しい事業に取り組みに対する支援を行う補助金は「事業再構築補助金」。
小規模事業者が、販路開拓等の取り組みに対する支援を行う補助金は「小規模事業者持続化補助金」。
このような補助金があるので、適切な補助金を利用するために、以下のポイントを事前に確認しておくことが重要です。
| 確認項目
・事業と補助金の目的や趣旨の合致 |
今回のコラムは以上となりますが、補助金を申請し、実際にお金を受け取るまでの流れを知りたい方はこちらから続きをご覧ください。




