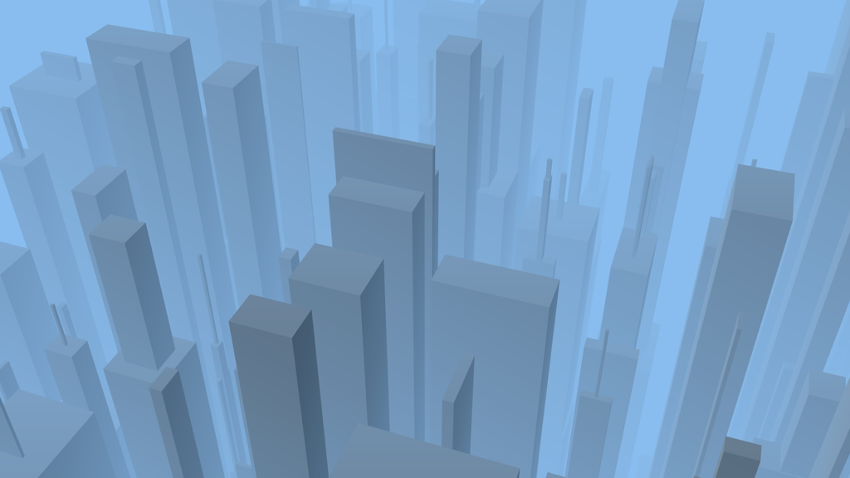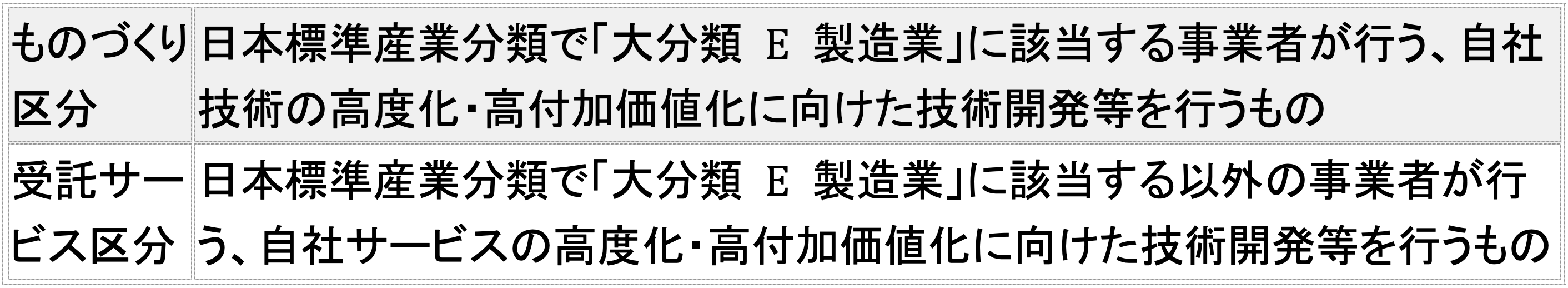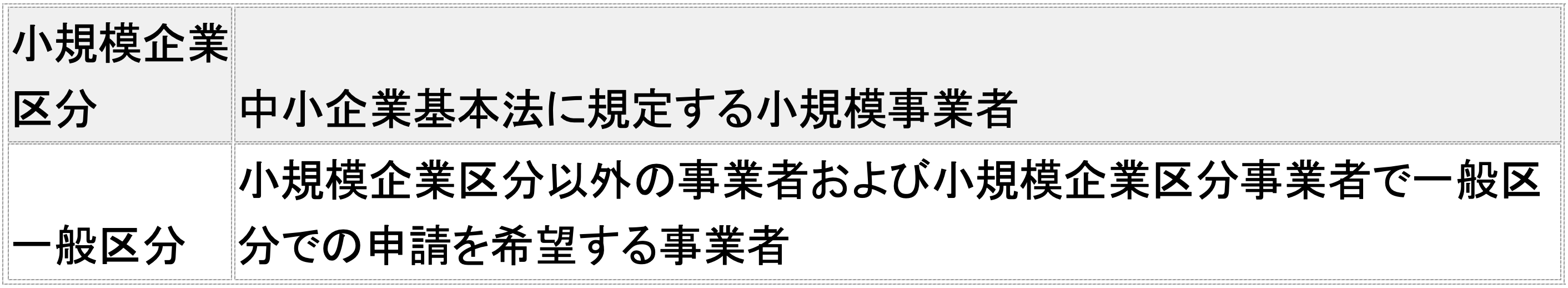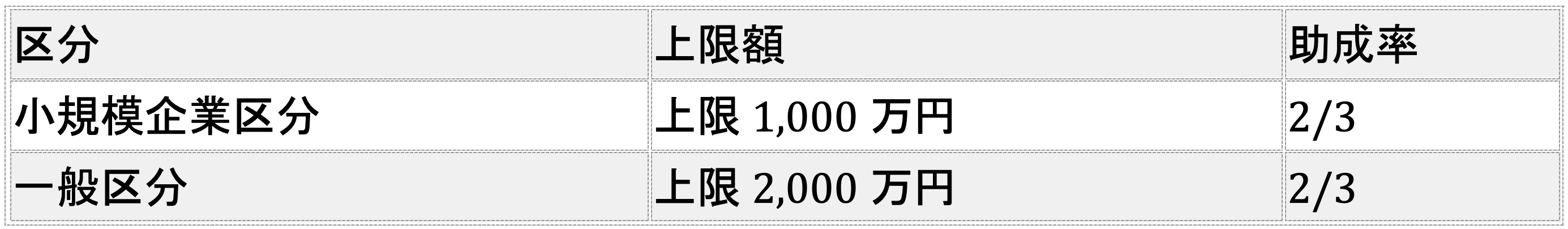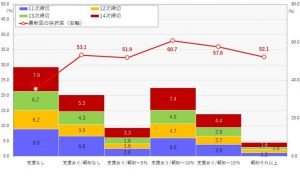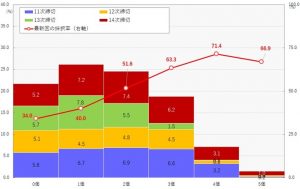・省エネ設備の導入を検討している方
・大型の設備投資を検討している方
省エネ性能の高い設備・機器への更新を検討されている製造業の方に今回ご紹介するのが、
「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」です。
本記事では「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」について、どのようなものか
概要を紹介します。補助金の申請を検討するにあたっての参考材料として、ぜひお役立てください。
省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金とは?

省エネ型設備への更新に使えるのが「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」です。
この補助金では、過去にない大きな予算額で省エネ設備投資の支援を行っています。
2023年の3次公募は締め切られましたが、今後も募集が行われるかもしれません。
設備や機器の更新予定があるのなら、公募要領をチェックしておくとよいでしょう。
(参考)3次公募用 令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金公募要領
省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金の概要

省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金の概要を紹介します。
ここで参照するのは、第3次公募用の公募要領です。
今後また受付が始まった場合、公募要領の内容に変更や修正が生じる可能性があります。
そのため申請にあたっては、常に最新の公募要領を参照してください。
補助対象事業
省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業の補助対象事業は3種類あります。
- (A)先進事業
- (B)オーダーメイド型事業
- (D)エネルギー需要最適化対策事業
ほかに(C)指定設備導入事業もありましたが、現在は対象外です。
3つの対象事業について紹介します。
(A)先進事業
先進事業は、SIIが設置した外部委員会で審査・採択して公表した補助対象設備への更新で、
以下いずれかを満たす事業が対象です。
- 省エネルギー率+非化石割合増加率:30%以上
- 省エネルギー量+非化石使用量:1,000kl以上
- エネルギー消費原単位改善率15%以上
(引用:3次公募用 令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金公募要領)
(B)オーダーメイド型事業
オーダーメイド型事業は、目的や用途に合わせて設計あるいは製造する、オーダーメイド型設備への更新が必要です。先進事業と同じように、達成目標の数字が決められています。
- 省エネルギー率+非化石割合増加率:10%以上
- 省エネルギー量+非化石使用量: 700kl以上
- エネルギー消費原単位改善率7%以上
(引用:3次公募用 令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金公募要領)
(D)エネルギー需要最適化対策事業
エネルギー需要最適化対策事業は、SIIが公表したエネマネ事業者と契約を締結します。そのうえで導入した機器によって省エネ化を図り、運用改善を行う事業が対象です。原油換算量ベースで、省エネルギー率2パーセント以上を達成する必要があります。
補助対象外となる事業
本事業の補助金申請にあたっては、多くの要件が設けられています。
また補助対象外となる事業についても確認が必要です。対象外となる事業の一部を紹介します。
- ・新たに事業活動を行う新築および新設の事務所に導入する設備
- ・事業活動に供していない設備の更新
- ・居住エリアでの設備更新
- ・売電を目的とする事業
省エネが可能であっても、売電が目的の場合は対象外となりますので注意してください。
補助金額と補助率
省エネを目的とした設備に使えるだけあって、本補助金の補助額は高額です。
補助金額は対象事業・年度などの要素で違ってきます。
| 補助金額の上限 | 単年度で最大15億円/複数年度で最大40億円 |
補助率は次の通りです。
| (A) 先進事業 | ・中小企業2/3以内 ・そのほか1/2以内 |
| (B) オーダーメイド型事業 | ・中小企業1/2以内 ・そのほか1/3以内 |
| (D) エネルギー需要最適化対策事業 | ・中小企業1/2以内 ・そのほか1/3以内 |
対象事業等による違いがあるので、どちらに該当するか確認してみましょう。
今回は以上となります。
・「どんな業種が対象となるのか」
・「対象となる経費は何か」
気になる方はこちらから続きを読むことができます。