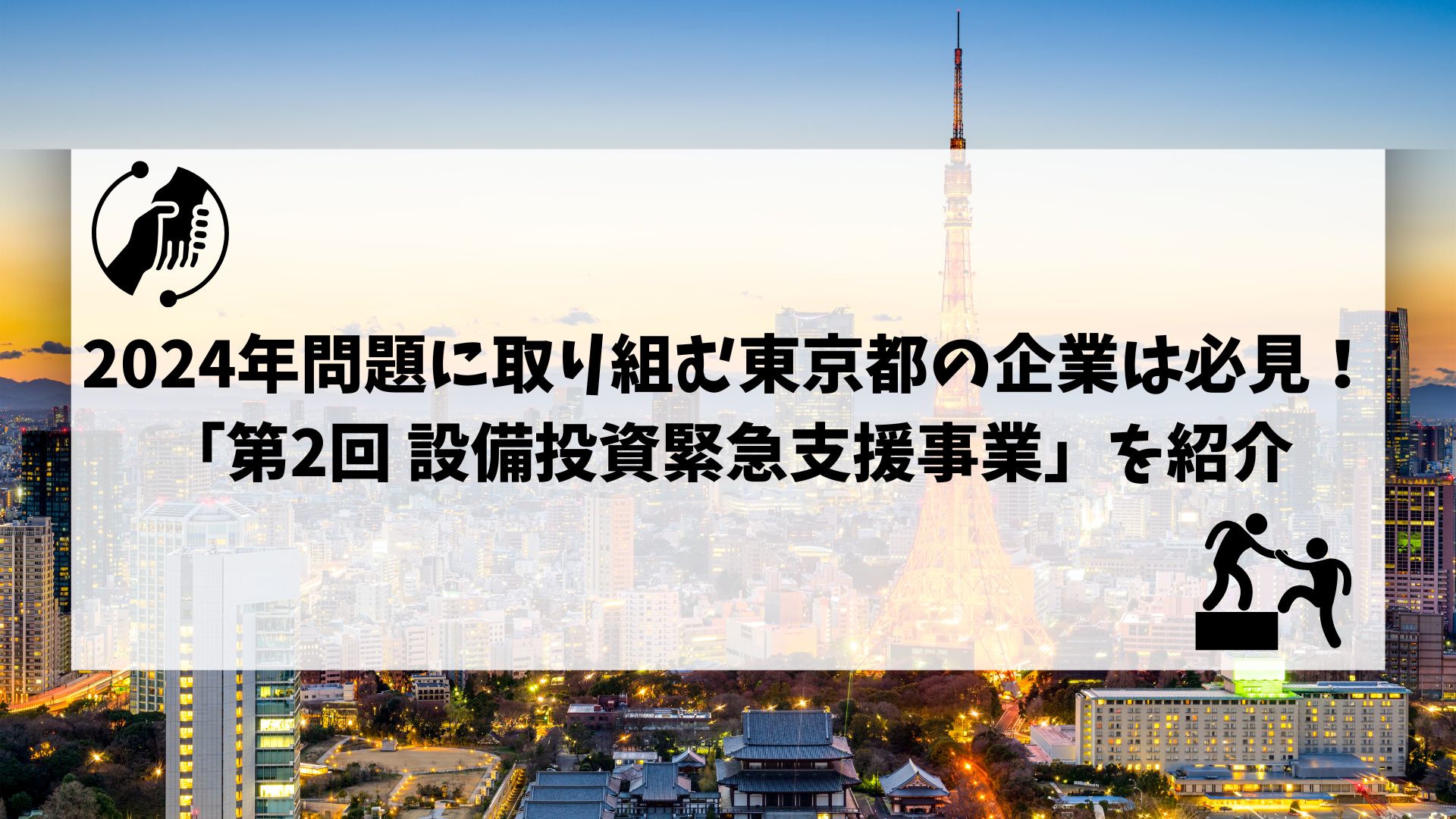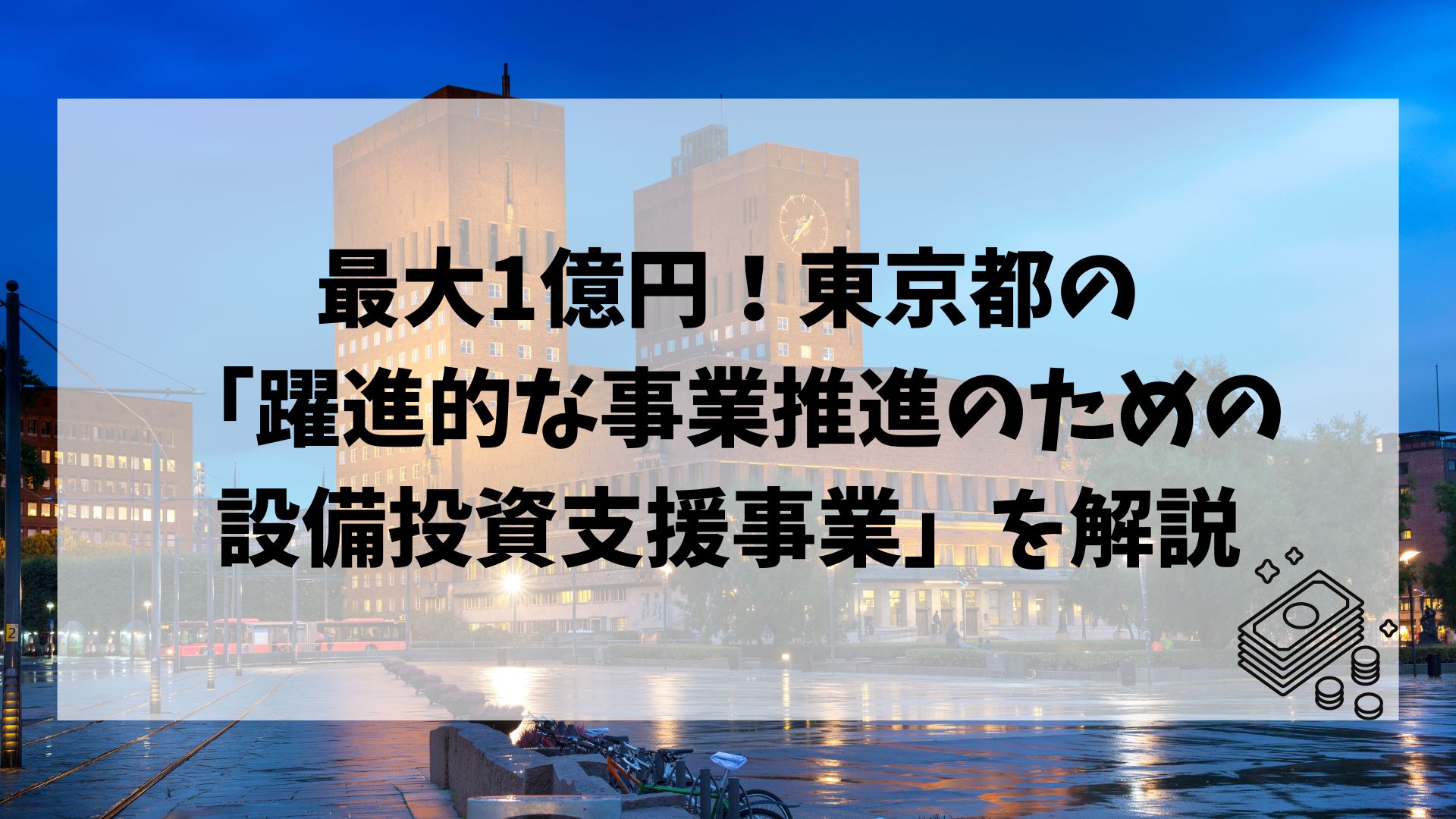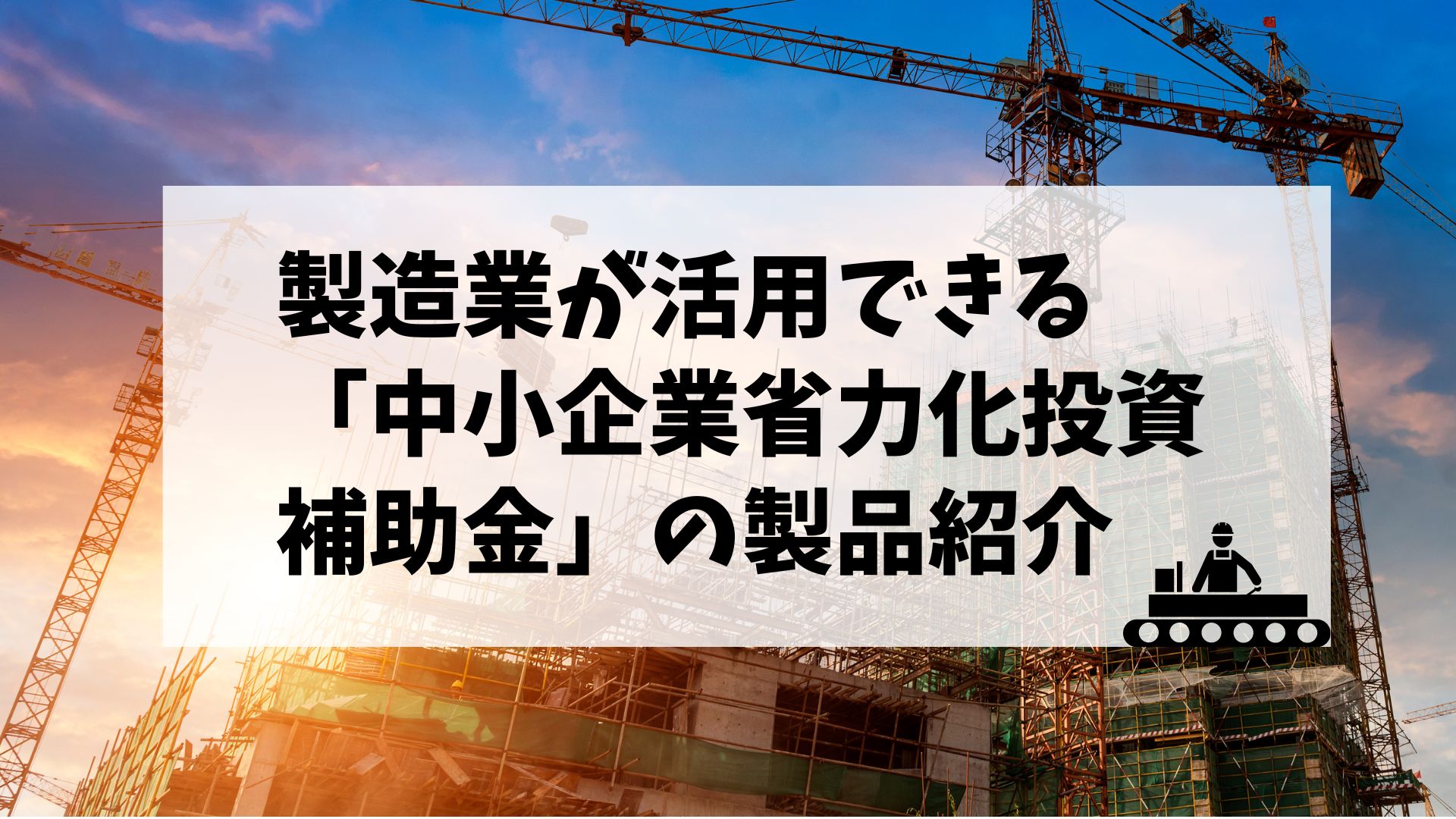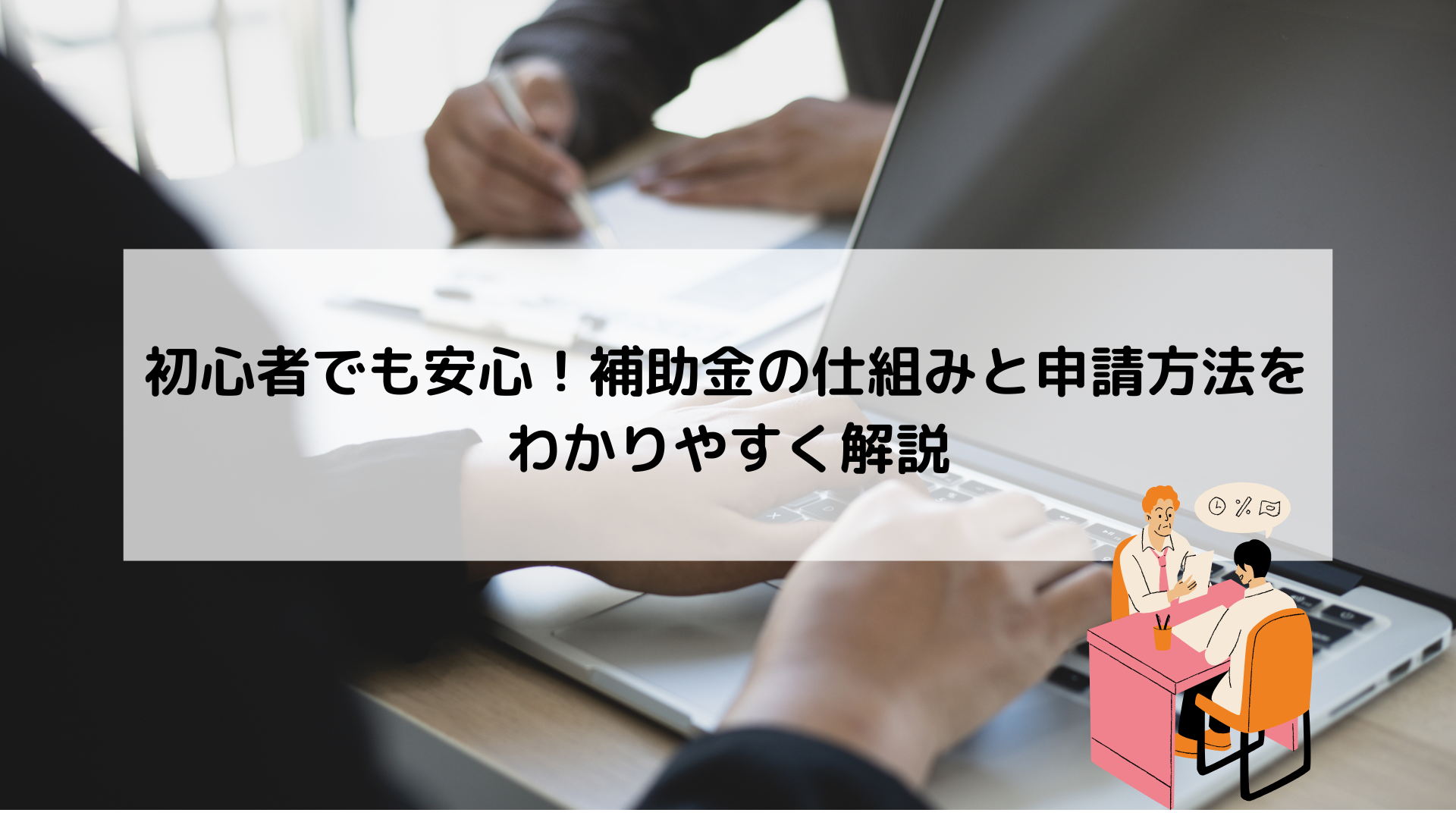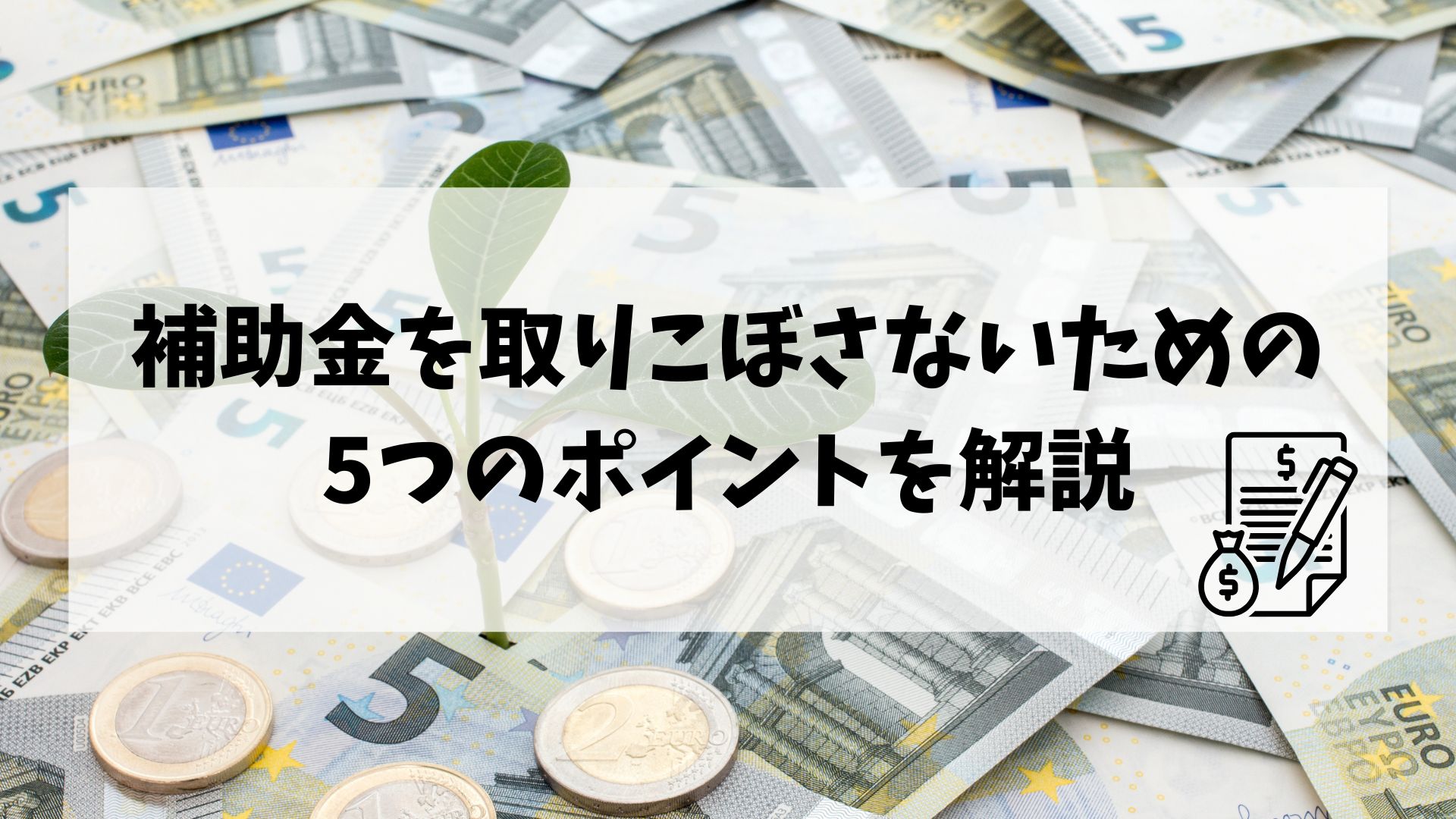
補助金は、企業の成長や新しい事業展開をサポートする強力な手段です。
しかし、多くの企業が補助金をうまく活用できずに、そのチャンスを逃してしまうケースが見られます。
この記事では、「補助金取りこぼし」の原因を解説し、具体的な対策を紹介します。
補助金取りこぼしの5つの要因
①補助金の種類が多く、適切なものがわからない
日本には数多くの補助金が存在し、それぞれ目的や対象が異なります。
多くの事業者は、自社に最も適した補助金を特定できず、申請の機会を失ってしまうことが少なくありません。
特に初めて申請を行う企業にとって、数多くの補助金の中から、自社に最適な補助金を見つけることは大きな課題です。
②公募要領が難解で理解できない
補助金を申請するためには、公募要領という公式のガイドラインに従う必要があります。
しかし、この公募要領は文字だらけで表現も堅苦しく、専門用語が多く含まれているため、読み解くのに苦戦しているところも多いようです。
よって、公募要領の読み解きに時間がかかったり、正確に理解できないまま申請して、条件を満たせず不採択となることもあります。
③申請準備が複雑で時間がかかる
補助金の申請には多くの書類や資料が必要であり、事前準備が非常に大変です。
特に初めて申請する企業は、何から手をつけるべきか迷い、必要な書類を揃えるのに時間がかかってしまうことがあります。
これにより、締め切りに間に合わないケースも少なくありません。
④日々の業務で、補助金情報の収集が不十分
通常業務に追われてしまうと、補助金の調査を後回しにし、補助金に関する重要な情報を見逃しがちです。
補助金には公募期間が限られており、タイミングを逃すと申請機会を失ってしまいます。
特に突発的な公募や短期間で締め切りが来る補助金の場合、情報を見逃すことで取りこぼしが発生します。
⑤設備・システム購入タイミングが補助金と合わない
補助金は審査制で、原則は採択された後に支払いを行うため、審査結果より前に購入を進めてしまうと、補助対象外になります。
また、購入のタイミングと補助金の公募期間が合わない場合、補助金を使って購入することができないため、結果として補助金を利用できないケースもあります。
今回のコラムは以上となりますが、補助金を取りこぼさないための対策を知りたい方はこちらから続きをご覧ください。